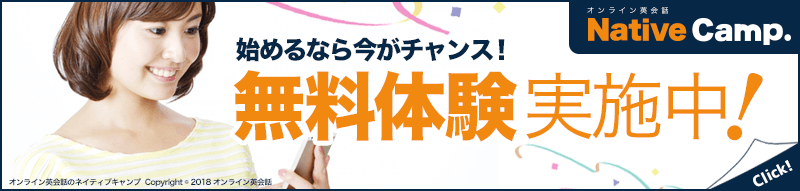最終更新日:2019-07-14

みなさんこんにちは。
みなさんは
「良いことが起きますように」
「不幸なことが起きませんように」
などの理由でお祝いをしたり厄除けをしたりすることはありますか?
現代でも昔からの風習で弦(げん)を担ぐために何かを買ったり行なったり、またはどこかに行ったりなどしますよね。
そこで、みなさんに質問です。
大学受験や資格試験の時にも使う合格祈願の縁起物として知られる手足のない人形は以下のうちどれでしょう?
1~3の選択肢の中から一つ選んでください。(カッコ内は英単語です。)
1 まねき猫(Beckoning cat)
2 だるま(Dharma)
3 こけし (Limbless wooden doll)
・・・答えは当然、2のだるまですね。
この問題、日本人のみなさんにとっては当たり前過ぎて呆れられてしまうかもしれません。しかし外国人にとってはどうでしょうか。
みなさんは外国人からだるまについて詳しく聞かれたら説明できるでしょうか。だるまは日本でも昔から伝わる置物ですが、どのように、何のために使うのか、またその由来まで聞かれると答えられない・・・という人もいるのではないかと思います。
だるまは日本的なデザインで、外国人にも嬉しいお土産にもなります。
今回は、だるまを英語で表現できることを目標に、だるまについてご紹介します。
だるまって何に使うの?ただの置物なの?
だるまは単なる置物ではなく日本の縁起物です。何か願いごとをする時に使います。
だるまを説明する前に達磨(だるま)のことを説明します。達磨はインドから中国に仏教を伝えた僧侶です。
中国の禅宗の開祖とされているインドの僧侶です。達磨大使ともいいます。
座禅姿の達磨大使を模した置物がだるまです。
座禅とは姿勢を正して座った状態で精神統一をする、禅の基本的な修行法のことです。
だるまの歴史を知ろう
鎌倉時代に日本に禅宗が伝わりました。禅宗の開祖が達磨大使と言われています。伝説によると達磨大使は壁に向かって9年の座禅をして手と足が腐ってなくなってしまったそうです。
だるま人形はもともと中国から伝わってきた「起き上がり小法師」でした。起き上がり小法師は下の方に重りが入っていて転ばせても再び起きあがる人形です。
江戸時代に起き上がり小法師のモデルを禅宗開祖の達磨大使にして作ったのが、だるま人形の始まりです。達磨大使は赤い服を着ていたので、多くのだるま人形が赤色です。
怖い顔をしただるま人形が倒しても倒しても起きあがってくることで、だるま人形は江戸時代の子どもに人気になりました。
だるまの色
実は中国から入ってきただるまは赤色ではなく黄色でした。だるまは赤に限らず色々な色があり、それぞれの色に意味があります。
例えば高崎だるまの例ですが、
赤:家内安全・開運
青:学業向上・才能向上
黄:金運・幸運向上
緑:身体健勝・才能開花
金:金運・仕事運向上
白:受験合格・目標達成
黒:商売繁盛
このように色によって意味があります。プレゼントしたり自分で買う時は、自分が求めているものを叶えてくれる可能性を秘めているだるまを選びたいですね。
だるまの絵付け体験ができるところもある
外国人の中には、だるまの絵付けを体験してみたい人もいるかもしれません。
例えば群馬県の高崎市にある「だるまのふるさと大門屋」では絵付け体験もできます。群馬県の高崎だるまは、日本でも有名なだるまの一つ。体験費用は約800円~で電話で予約もできるそうです。
だるまの本場、群馬県に立ち寄る機会があれば体験しても面白いでしょう。特に体験できることは外国人にも喜ばれやすいです。
群馬県は少し遠いという人もいるかもしれません。東京の調布市には、可愛い2センチの無地のだるまに絵付けできるところがありますので、ぜひ調べて行ってみて下さいね!
日本の有名なだるまを知ろう
日本で一番、だるまを生産しているところをご存知でしょうか。実は群馬県がだるまの生産でかなり高いシェアがあります。
高崎だるま
群馬県の高崎市は、日本のだるまの全国生産量のうち8割。選挙でよく見るだるまのほとんどが実は高崎だるまだと言われています。
群馬県はからっ風、乾燥した気候で、だるまをつくりやすい環境で養蚕農家の内職に適していました。そのため高崎市の内職として、だるまづくりが盛んになり、高崎のだるまとして有名になりました。
松川だるま
仙台市近郊のだるまです。胴体の前半分が青く後ろが赤、眉毛に実際の毛が使われているのが特徴。
仙台の戦国時代の武将は独眼の伊達政宗ですが、政宗に配慮して松川だるまは最初から両目が描かれている点が違います。
白河だるま
福島県の白河市で作られているだるま。眉が鶴、ひげは亀、あごひげは松、びんひげは梅に見立てられ、さらに顔の下には竹を模様化した「鶴亀松竹梅」を取り入れた縁起の良いだるまです。
松平定信が城下の繁栄を願い生まれました。
赤いだるまだけでなく開運の利益がある白だるまも作られています。
英語でだるまを説明しよう
みなさんはだるまに何かお願い事をしたことはありますか?
また、目標を決めた時に片目を入れて、達成した時にもう片方も描くというのが有名ですが、英語で説明するのは少し難しいですよね。
今回は簡単に5つのステップでまとめてみました。
1 目標を決めます。
(decide a goal)
2 だるまに目を入れます。
(paint in an eye)
3 目標を達成するまで、片方の目は書かずに飾っておきます。
(until achieving one’s goal, do not paint in another eye and display dharma.)
4 目標が達成できたら、もう片方の目も入れます。
(after achieving one’s goal, paint in another eye.)
5 祈願達成で両目の描かれただるま人形の完成です。
(after achieving one’s goal, complete dharma doll with two painted eyes.)
受験や資格試験、選挙の時にも合格や当選の願いをこめて使われます。外国人にだるま人形をどう使うのか説明する時は、この5ステップを教えてあげれば良いでしょう。
また、だるま自体を知らないという外国人に、英語でだるまを説明するための例文を見ていきましょう。
・Dharma doll is modeled after Bodhidharma who was a founder of Zen Buddhism.
(だるま人形は禅宗の開祖の達磨がモデルです。)
※Bodhidharma :達磨
※Zen Buddhism:禅宗
※found:設立する
※model after:~を真似る
・Dharma doll is loved by the Japanese as a talisman.
(だるま人形は、願いを叶える縁起物として日本人に親しまれています。)
※talisman:縁起物
・Dharma has some colors and each color has it’s own meaning.
(だるまにはいくつか色があり、それぞれに意味を持っています。)
達磨大使の禅とは?
だるま人形のモデルになった達磨大使は禅宗の開祖と呼ばれています。禅は海外でも知られており人気があります。
アップルのスティーブ・ジョブスも禅の考えに影響を受け、福井県の禅の寺として有名な永平寺で修行を考えたことがあるというエピソードまであります。
禅はサンスクリット語の「ディヤーナ」が語源です。
ディヤーナを中国語にすると「禅那」で、禅は禅那の略語です。サンスクリット語とは古代インドで使われていた言葉です。
精神を統一して悟りを開く修行や姿勢が禅です。
禅では自己は迷いや束縛の元であるとされ、自分のあるがままの姿に気づくために座禅などで心の余計なものを捨て迷いを断ち切ります。
禅では長時間あぐらをかいて座り続ける「座禅」という修行があり、無心で本来の何もなかった頃の自分に立ち返ります。座禅中は雑念を捨てます。
だるま人形のモデルの達磨大使は、この座禅の修行で手足がなくなってしまったと言われています。
外国人にとって「禅」の考え方は人気なので、簡単に「禅」についても覚えておくと良いでしょう。
座禅を体験できるお寺もあるので興味のある外国人に紹介したら喜ばれるでしょう。
だるまに似たものは海外にもある?
実は海外にもだるまに似た人形があります。
ロシアのマトリョーシカ
マトリョーシカはロシアの民芸品。
丸いフォルムで手足がないところは日本のだるまにも似ています。ただしマトリョーシカは女の子がモデルです。
こけしとだるまを足して2で割ったような人形です。面白いのは人形の中に小さな人形が入っているところ。入れ子構造になっています。
マトリョーシカも縁起物で贈り物にオススメです。願いを叶えてくれる人形とも言われており日本のだるまに用途も似ています。
ミャンマーのピッタインダウン
ミャンマーにも日本のだるまとフォルムが似ている人形があります。「ピッタインダウン」とは「投げる度に起き上がる」という意味です。いくら投げられても、揺れながら最後に笑顔で立ち直るため縁起の良いものです。
日本のだるまも七転び八起きで何度でも起き上がるから縁起が良いと言われていますが、ミャンマーのピッタインダウンと良く似ています。
その他の縁起物
だるま以外の日本の縁起物をここで見ていきましょう!
まねき猫
これは有名ですね。商売繁盛の縁起物としてお店などに置かれていますね。右手を挙げたまねき猫は、金運をまねくと言われているそうです。
熊手
こちらも商売繁盛のための幸運や金運をかき集めるとして酉の市(とりのいち)などで販売されている縁起物になります。
破魔矢
邪気や汚れを払い魔除けや厄除けになる矢で、お正月や端午の初節句などの際に家に飾る縁起物ですね。
こけし
こけしは、江戸時代末ごろに東北地方の温泉地のお土産として売られていた轆轤(ろくろ)挽きの木製の人形です。球型の頭と円柱の胴だけのシンプルな形が特徴です。
恵方巻き
最近では節分に恵方巻きを食べる方も多いのではないでしょうか?
節分の際に恵方(歳徳神のいる)を向いて無言で食べると縁起が良いとされていますが、その方角はその年の干支によって指定されています。
上記の他にも日本には多数の縁起物があるのでインターネット検索してみるのも良いかもしれませんね。
まとめ
今回の記事では「だるま」についてご紹介させていただきました。
だるまは何かを願う時に使える日本の縁起物の人形です。禅の開祖の達磨大使をモデルにした丸いフォルムで、外国人にも人気の高いお土産のひとつ。英語でだるまの説明や目の入れ方、何に使うかなどを説明できるようにしておきましょう。
日本人だからこそ英語で自分の国の文化を説明できるようにすると国際人に近づけます。また、達磨大使の開いた禅は外国人にも人気のある宗派なので、禅のことも簡単に知っておくと良いのではないでしょうか。
ネイティブキャンプには日本が大好きな講師がたくさんいます。
日本語を勉強中の講師や、日本の文化を知りたいと思っている講師がたくさんいるので、ぜひ今回学んだことを活かして日本の文化を紹介してみてくださいね!

石川県出身。明治大学法学部の国際法コースで英米法を専攻。卒業後、日本の小学校教諭を経てタイ王国の首都バンコクの国立大学RMUTRの教養学部・日本語学科にて専任講師。日本語の講義や日本・タイの私立大学の交換留学提携、タイ全土の日本語コンテンストの審査員を経験。帰国後は留学生支援の財団法人・外資系小売業を経てライター職。好きな食べ物はカレー。東京に行く度にカレーの聖地、神保町のカレー屋巡りをしています。