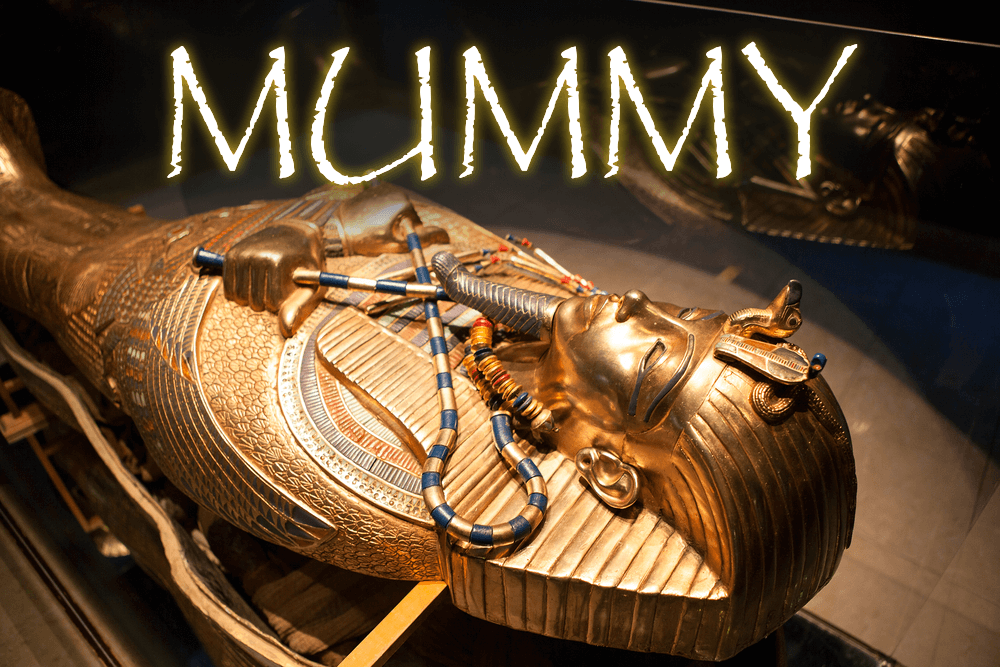
今回ご紹介するのは、「ミイラ」の英語表現です。日本語では「ミイラ取りがミイラになる」なんていう諺(ことわざ)もありますね。
そもそもなぜミイラを取りにいくのか? なぜミイラに価値があるのか?考え出すと次から次へ疑問が生まれますが、実は語源にヒントが隠されているんですよ。
今回はそんな「ミイラ」の英語表現について、例文やエピソードを交えつつ解説します。
「ミイラ」は英語で?
ミイラを意味する名詞は「mummy」。そのほか、「corpse」「embalmed body」などの表現も用いることができます。
語源や例文を見ていきましょう。
「ミイラ」の語源
ミイラとは、腐敗することなく乾燥した、人間や動物の遺体のこと。遺体を保存する目的で人為的に作ることもあれば、自然条件で自然にミイラ化することもあります。
ミイラというと、エジプトのピラミッドから出土する王族の遺体というイメージが強いかもしれませんが、実は世界中で発見されています。
「mummy」の語源は、アラビア語でタールやアスファルトを指す「mummiya」が語源といわれています。諸説ありますが、7世紀頃にアラブ人がはじめてエジプトのミイラを見たとき、瀝青(原油由来の炭化水素化合物のこと)で覆われていると考えたのが由来です。黒光りする肌の色がそう思わせたようですが、実際には濃色の樹脂が用いられていたようです。
「ミイラ」の英語表現
それでは実際に、「ミイラ」の英語表現を見ていきましょう。
Mummy
ミイラは英語で「mummy」と綴ります。発音は“マミー”。子どもが母親に呼びかけるときの“mummy”と同じ発音です。
この間、博物館で開催されている特別展示でミイラを見てきたんだ。とても興味深かったよ。
古代エジプト人は、遺体を保存する目的でミイラを作り出す技術を編み出した。
墓荒らしは、副葬品だけでなくミイラも盗掘した。
博物館に展示されたミイラは、多くの来館者を惹きつけた。
古代遺跡に興味のある方は、エジプトの死者の都を舞台に繰り広げられるアクション映画『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』をご覧になったことがあるのではないでしょうか。本作の原題は、そのものずばり『The Mummy』です。
専門家の感想が気になるところではありますが、古代エジプトの文明をエンタテイメントに昇華した、見応えのある映画ですよ。VFXを駆使して描かれたミイラのシーンは、なかなか怖い!
Corpse
「Corpse(コープス)」は「遺体」を意味する単語です。
語源はラテン語のcorpusで、身体、物体、死体、構造など多様な意味を持ちます。この単語から、会社組織を表すcorporation(コーポレーション)、文章を集積してコンピュータで検索できるようにデータベース化したcorpus(コーパス)、軍隊の部隊を意味するcorps(コープス)など、さまざまな単語が派生しました。
たとえば、アニメーション映画『ティム・バートンのコープスブライド』は、直訳すると「死体の花嫁」となります。
類義語に「dead body」がありますが、これは文字通り死んだ身体=「死体」を意味します。dead bodyが日常的な表現であるのに対し、「corpse」は医学や法学など、よりアカデミックな文脈で使用されます。
生命のない物体というニュアンスで、「body」のみで死体を指すことも。再び映画の例ですが、『スタンド・バイ・ミー』の原作となっているスティーブン・キングの小説のタイトルは、『The Body』。「死体」という意味です。
『ハムナプトラ』にせよ『スタンド・バイ・ミー』にせよ、英語の原題はシンプルで直接的なものが多く、言語感覚の違いがわかって面白いですよ。
先日の大雨によって、山の斜面から身元不明の遺体が発見された。
スティーブン・キングの小説『ザ・ボディー(スタンド・バイ・ミー)』では、4人の少年たちが死体探しの旅に出かける。
刑事ドラマでは、しばし刑事たちが死体安置所で死体を検分する場面が登場する。
Embalmed body
ミイラを表現する英語として、「Embalmed body(エンバームド・ボディ)」も使用できます。防腐処理を施された遺体を指します。
エンバーミングとは、遺体の長期保存を可能にするための技法のこと。現代の技術では10日間〜2週間程度、衛生的な状態で遺体を保存できます。
紀元前3200年に行われていた古代エジプトのミイラづくりは、人類史上の最初期に発展したエンバーミングの技術であるといえます。
防腐処理された死体は、遺族が故人の死を悼むのに十分な時間を与えてくれる。
古代エジプトでは来世を信じていたため、ファラオの死に際して遺体に防腐処理を施した。
「ミイラ」に関する英語表現
最後に、ミイラに関わる英語表現をご紹介します。
mummification
ミイラ化することを、「mummification(マミフィケイション)」といいます。これは動詞「mummify(マミファイ)」の名詞形です。
「mummify」「mummification」の例文を下記でご紹介します。
気象条件によっては、遺体がミイラ化することもある。
古代エジプトでは、ファラオが亡くなるとその遺体をミイラ化された。
古代エジプト人は高度なミイラ化技術をもっていた。
ピラミッド時代のエジプトでは、王が亡くなると埋葬の儀式が行われました。このとき王の遺体をミイラ化するのは、神官の仕事だったようです。遺体から臓器を取り出し、40〜70日ほど乾燥させた後に墓へ運ばれましたと考えられています。ファラオのミイラは、最終的にはピラミッドの玄室という空間に収められます。
ところが、亡骸とともに埋葬された金銀財宝を目当てに、ほとんどの王墓が盗掘に遭っています。このとき盗まれたのは副葬品だけではありませんでした。ミイラそのものが盗掘の憂き目に遭っていたのです。
語源の項で解説したように、ミイラは瀝青(ムンミア)で覆われていると考えられていました。この瀝青には薬効があり、さまざまな病気に効く万能薬として珍重されていたのです。
瀝青(ムンミア)で防腐処理を施された遺体そのものがムンミア(mummy)と呼ばれるようになり、時代が下って、ミイラ=万病に効く万能薬だと信じられるようになったそう。
そんな事情で、ミイラは価値あるものと見做され、あらゆる病気に効く“ミイラ薬”として世界中へ輸出されていたのです。
冒頭で「ミイラ取りがミイラになる」という諺をご紹介しました。ミイラを取りにいった本人がミイラになってしまうということから、転じて、人を探しにいった人が帰らぬ人になるとか、誰かを説得しにいったら逆に相手に諭されて取り込まれてしまうといった意味で用いられます。この「ミイラ取り」とは、ミイラ薬を取りにいくことを指しているんですね。
「ミイラ取りがミイラになる」に近しい英語表現として、「Many go out for wool and come home shorn.(羊の毛を刈りにいって刈られて帰る者が多い)」という諺があります。
まとめ
「ミイラ」や、ミイラに関連する英語表現をご紹介しました。
語源を紐解くことによって、言葉の背景にあるさまざまな歴史に触れられるのも、語学学習の醍醐味のひとつ。興味のある分野に関連した単語を詳しく調べていくと、より英語の学習も捗るかもしれませんよ。

◇経歴(英語を使用した経歴)
アメリカの四年制大学に留学
◇英語に関する資格(資格、点数など)
大学入学時にTOEFL580点を取得
◇海外渡航経験、渡航先での経験内容(仕事、留学、旅行など)
高校卒業後に留学し、アメリカ、ニューヨークの四年制大学を卒業
アメリカ国内の他に、カナダ、ドイツ、ポーランド、香港を旅行得
◇自己紹介
ライター/編集者/時々漫画家
出版社、広告代理店を経て、現在は編集プロダクションに勤務しながらフリーランスのライターとしても活動。さまざまなマイノリティが住むブルックリンに滞在していた経験から、人種・ジェンダー・貧困などの社会問題に関心を持つようになり、現在の活動の軸となっている。好きなものは大型犬。

I took a Bachelor of Science degree in Mathematics where my problem-solving and critical-thinking skills were honed. I have worked as a trainer in a government office, which has helped me to develop my communication and intrapersonal skills. My hobbies are reading, listening to music, and cooking. After joining NativeCamp, I acquired 2 years of teaching experience. Currently, I am involved in content production in the Editing Department.




