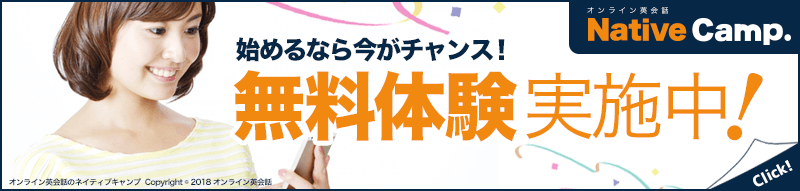英語で1月から12月まで、そして月曜日から金曜日まで、みなさんは英語で正しく言えますか?
「月や曜日は、日常会話頻出用語。
そんなの基本中の基本!中学校で習ったから分かるわいっ!」
という方も多いかもしれませんが、順番通りなら全て言えても、英会話の中で突然聞かれた際に、
「あれ、11月ってなんだっけ?」
「月曜はMondayだから、水曜日は…」
と考えこんでしまっていませんか?
今回は、英語で月や曜日の呼び方を完璧に覚えられるように、みなさんをお助けしたいと思います。
これを機に一度頭の中を整理して、改めてマスターしちゃいましょう!
- 日付を英語にしてみよう
- 月の名前の由来とは・・・?
- お子様におすすめ!英語の歌で覚えよう。
- 語呂合わせで覚えよう
- フラッシュカードを使って覚える
- ネイティブキャンプで月や曜日の言い方を覚えよう!
- おわりに
日付を英語にしてみよう
はじめに、現代の暦の成り立ちから、どうしてその呼び方をするようになったのか、その由来を確認して、その後にそれぞれの暗記法についてご紹介していきます。
まずは曜日や月の呼び方とともに、日付の表現を確認しましょう!
月曜日 Monday
火曜日 Tuesday
水曜日 Wednesday
木曜日 Thursday
金曜日 Friday
土曜日 Saturday
日曜日 Sunday
1月 January
2月 February
3月 March
4月 April
5月 May
6月 June
7月 July
8月 August
9月 September
10月 October
11月 November
12月 December
1 first 2 second 3 third
4 fourth 5 fifth 9 ninth
10 tenth 12 twelfth
17 seventeenth 20 twentieth
23 twenty-third 28 twenty-eighth
30 thirtieth 31 thirty-first
英語の日付の順番は?
日付を日本語で伝えるとき、 年→月→日→曜日 の順番にするのが一般的です。
例)2019年2月25日火曜日
英語でこれを伝える場合も同じ順番で良いのでしょうか。
実は、これを英語にすると、 曜日→日→月→年 というように順番が逆さまになります。
例)Tuesday, 25th February, 2019
月の名前の由来とは・・・?
さて、これまで見てきたように、1月は1が付くのに、firstでも、oneでもなく、それぞれの月に名前を持ちます。
では、どうしてこのような呼び方となったのでしょうか。
その答えは、古代ローマ帝国の時代に遡ります。
カレンダーの暦の元となったのは、紀元前後のローマ帝国によって制定されたユリウス暦からで、そこから現代の月や曜日の名前が付けられたからです。
①現在の暦の成り立ち
1582年にグレゴリウス13世が、グレゴリオ暦The Gregorian Calendarを採択したことで、今日の暦の形を取りました。
それ以前は、紀元前46年からおよそ1500年以上もの間ユリウス暦が使用されていました。
しかし、閏月の数え方によるズレが生じてしまい、正しい日にキリストの重要な祝祭である、春分の日を祝えなくなったため、より精度の高いグレゴリオ暦に改暦されました。
日本でも、1900年からこのグレゴリオ暦が使用されています。
現在の、1年を1月から12月までと分けるのはユリウス暦が元になっており、その名前も同様です。
そして、このような月や曜日の名前は、ユリウス暦が制定された、紀元前後の時代に崇められた神々の名をとって、名付けられたのです。
その多くは、ローマ帝国やその周辺地域でもてはやされた、ギリシャ神話やローマ神話の神々に基づいて名づけられています。
とはいえ、すべての月が神々の名前と対応しているわけではなく、7月と8月は実在した偉人の名であったり、9月からは7番目の月、10月は8番目の月…と、順番で示されたりするように、月の名前が必ずしも神々に由来しているわけではありません。
それでは早速、月の名前の由来から確認していきましょう。
②暦と神々
それでは、それぞれの月や曜日は、具体的にどのような神々と対応しているのでしょうか。
また、それらがローマ人やその周辺の民族にどのような役割を持っていたのか見ていきましょう。
1月 January
ヤヌス(Janus)
ヤヌスは、ローマ神話の中で天国の扉を司る役目があります。
体は一つですが、前と後ろでそれぞれ2つの顔があり、双面神の姿を持つとされます。
そして、物事の内側と外側を同時に見ることができるとされていました。
過去と未来を繋ぎ、時間を司る神とされ、双面の片方の面は、未来を見つめる若者の顔、もう一方は過去を見つめる老人の顔とされています。
1年の最後と最初を繋ぐ扉の守護神として、1月はヤヌスの月となりました。
2月 February
フェブルウス(Februus)
農耕を営むローマ人にとって、3月から12月までが耕作に適した期間であり、1月と2月はお休み期間でした。
そのため、もともとは1月、2月という区切りは存在せず、後に1月と2月に分割されるようになります。
この期間は死の季節と呼ばれました。
そのため、死者の魂を清め、贖罪の力を持つとされたフェブルウスの名がつけられました。
ちなみに古代ローマでは、毎年2月に慰霊祭として、フェブルアーリア (Februaria)と呼ばれるフェブルウスを祀った祝祭が行われています。
3月 March
マルス(Mars)
マルスは戦と農耕を司る神とされています。
ローマ人にとって3月は、1月2月のお休み期間がようやく終わり、新たに畑作や軍事活動へと動き出す季節でした。
そのため、農作物の豊かな実りや、戦争での勝利をマルスに祈りました。
そのため、農耕と戦いを司るマーズが祀られました。
4月 April
アフロディーテ(Aphrodita)
ギリシャ神話に登場する、愛や美、また性を司るアフロディーテに由来します。
ローマ神話ではおなじみの、ビーナスに対応する女神とされます。
4月はローマ人にとって、綺麗な花が咲きほこり、植物が芽吹く美しい季節でした。
まさに美の神アフロディーテに相応しい季節ですね。
また、ラテン語「Aprilis」は「(花々が)開く」という意味を持ちます。
5月 May
マイア(Maia)
マイアは豊穣の女神、また春の女神とされています。
現在の労働感謝祭であるメーデーは、マイアに捧げる春の訪れを祝うお祭りでした。
農耕シーズン真っ只中のこの時期に、マイアに自然の再生と芳醇を祈ったとされています。
ギリシャ神話の中では、彼女は全能神ゼウスとの間に、ヘルメスを産んでいます。
6月 June
ユノ(Juno)
ローマ神話では全能神ユーピテルの妻、ギリシャ神話では全能神ゼウスの妻であり、ヘラクレスを息子に持ちます。
ゼウスの浮気性に悩まされ、数々の女神や人間の女性に激怒し、神話の中では幾度も残虐な姿を見せます。
7月 July
ジュリアス・シーザー(Julius Caesar)
7月はユリウス暦を制定した、ユリウス・シーザー(ユリウス・カエサル)の誕生月だったので、7月はカエサルの名前を付けました。
8月 August
ガイウス・オクタヴィアヌス(Augustus)
カエサルの養子であり、初代ローマ帝国皇帝であるオクタウィアヌス、アウグストゥスの誕生月だったので、8月はアウグストゥスの名前を付けました。
9月 September
9月は神々の名を元につけられたのではなく、「7番目の月」という意味を持ちます。
先述したように、古代ローマでは1.2月がお休み期間だったので、3月から数え始めて7番目の月という数え方をします。
10月 October
8番目の月という意味です。
ちなみに、タコは8本足なので、Octopusと呼ばれています。
11月 November
9番目の月という意味です。
12月 December
10番目の月という意味です。
続いて、七曜についても確認してみましょう。(カッコ内は省略表記)
月曜日 Monday(Mon.)
ルーナ Luna
月曜日は、月神ルーナと同一視されるローマ神話のディアーナに由来するとされています。
月の神様であるルーナに由来しているので、「Moon + Day」でMondayとなりました。
火曜日 Tuesday(Tue.)
テュール Tyr
ゲルマン神話のテュールは軍神として崇められ、火曜日はテュールの名を付けられました。
彼はローマ神話のマルスに当たるとされます。
水曜日 Wednesday(Wed.)
オーディン Odin
北欧神話の最高神「Odin」が「Woden」に変化して「~の」という意味の「es」が付き、
「オーディンの日」
という意味でこの名前になりました。
木曜日 Thursday(Thu.)
トール thor
北欧神話の雨や雷、農業の神であるトールの日という意味になります。
ローマ神話の全能神であり、天候を自在に操ることのできるユピテルに当たる神です。
金曜日 Friday(Fri.)
フレイア Freija
北欧神話でフレイアは愛と美の女神とされます。
万人を魅了する容姿を持ち、ローマ神話のビーナスと同一視されました。
土曜日 Saturday(Sat.)
サトゥルヌス Saturnus
ローマ神話の農耕神“Saturnus”に由来します。
人間に農耕技術をもたらしたとされています。
日曜日 Sunday(Sun.)
ソール Sol
ローマ神話の太陽神ソールに由来します。
ソールに捧げられた太陽の日という意味です。
お子様におすすめ!
英語の歌で覚えよう。
由来は分かったけど、全部を一度には覚えきれないよー!
という方のために、まずは歌で覚える暗記法をオススメしたいと思います。
曜日や月を覚える英語の歌は、英語圏でたくさんありますが、そのほとんどが海外では馴染みがあっても、日本人の我々には到底聞きなれないものが多いのです。
今回はマザーグースでおなじみの、10人のインディアンという曲に合わせて月の名前を順番に歌う“Months Of The Year Song”という曲を紹介します。
タイトルでピンとくる方は少ないかもしれませんが、だれもが幼いころに聴いたことのあるメロディーだと思います。
日本でもCMで使用されたり古くから親しまれている曲なので、一度聴いてみると、
この曲知ってる!
となるはずです。
次に、曜日を覚えるための歌を紹介したいと思います。
定番の Sunday Monday Tuesdayはみなさんご存知だと思うので、別なもので覚えやすいものを紹介します。
実はマザーグースのBINGOの替え歌として、こんなのがあるんです!
Do you know the 7 days?
Yes, I know the 7 days.
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
and Saturday.
and I know the 7 days
こちらはあんまりメジャーではないようで、ネット上にはBINGOの原曲バージョンしかあがってませんでした…。
これらの曲に合わせて口ずさんでみると、かなり頭に入ってくるはずです。
どれも軽快でポップな曲調となっているため、勉強や仕事の合間に歌ってみてはいかがですか?
語呂合わせで覚えよう
歌だけでなく、語呂合わせやダジャレで覚えるのが得意な方もいるのではないでしょうか。
そんな方のために、イチ押しのダジャレをお教えしたいと思います!
NHKの0655という番組で放送された、
「だじゃれde一週間」
という動画です。
こちらの動画では、ゆるい感じのかわいいキャラクターが、ダジャレで曜日を紹介してくれます。
月ようびが はじマンデー(Monday)
火ようび あいさつ「ち~す」デー(Tuesday)
水ようころんで うぇ~んズデー(Wednesday)
木よう雨かな?傘さーすデー(Thursday)
金よう ひるめし フライデー(Friday)
土ようび バッタリ会って ごぶサタデー(Saturday)
日ようくらい おこサンデー(Sunday)
のほほんとしたゆる~い雰囲気がクセになりませんか?(笑)
フラッシュカードを使って覚える
フラッシュカードの使い方としては、B5サイズの画用紙に、紙芝居のように絵が描かれているカードを見て、一瞬でその単語を言い当てるゲームがおススメです。
これをすることで、瞬発的な英単語力が養えられます。
一般的に、親子などで二人一組となって、カードを出す人と答える人に分かれて進めていきます。
できるだけ時間をかけず、直観やイメージで思い出させることで記憶に定着させる暗記法です。
通常、人間が勉強する際には論理性や言語能力を処理する左脳を使います。
しかし、フラッシュカードの暗記は、イメージや映像を処理する右脳を使った映像学習によるものです。
このように右脳を刺激して、イメージや絵などの周辺情報と一緒に覚えることができるのが特徴です。
ただし、右脳が活発に活動するのが思春期までとされるので、このやり方は早期教育に最も効果的ではありますが、大人には向かないようです。
ネイティブキャンプで月や曜日の言い方を覚えよう!
月や曜日の書き方・読み方を覚えたければ、どのようにネイティブキャンプのレッスンを活用していけばいいのでしょうか?
月や曜日については、キッズコースで学ぶことができます。
具体的には、LET’S GOやSIDE BY SIDEのテキストで月や曜日が盛り込まれている項目がありますので、ぜひ探してみて下さい。
月や曜日には、発音の難しいものもあるので、早いうちにカタカナ英語ではなく正しい発音を学んでおくといいですよ!
おわりに
今回は英語で月や曜日をマスターすべく、意外と知らないその由来から確認してきました。
月や曜日の名前となった古代ギリシャや古代ローマ人の神々についてはご存知でしたか?
また、これらの覚え方として、歌や語呂合わせ、フラッシュカードなどのツールを紹介しました。
月や曜日の名前に限らず、英単語を覚える上でも同じ方法で学習できますので、いくつか試してみて、自分に合ったものを見つけていけたらいいですね。
ネイティブキャンプでは、お子様の英語学習に役立つ「Let's go」や「Side by Side」を使ったレッスンを受けることができます。
ぜひ、覚えた曜日や月を使って講師たちと会話してみてくださいね!

札幌育ちの学生フリーランス。普段は英語科の大学に通い、オールイングリッシュの授業でネイティブから指導を受ける。主にウェブライターとして活動し、引きこもりながら細々と生活を送る。その反面、英語のスピーチコンテストをはじめ、ディベートやディスカッション、ポエトリーや英語劇など在学中に数々の大会に参加し、奮闘の末に受賞を果たす。スピーチ原稿を書いているときに、より多くの人自分の知識や価値観をシェアハピしたいと思い、ライターとしての活動を始める。