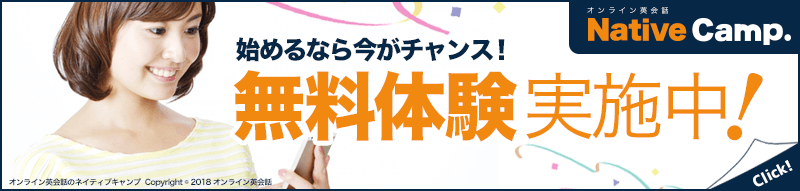TOEICやセンター試験、難関大学の入学試験の長文で頻出する「倒置」
倒置が起こっていることに気付かずに読み進めると意味を汲み取るまでに時間がかかってしまったり、途中で文脈を掴めなくなったりします。
しかし、倒置は使い方さえ覚えてしまえば怖くはありません。
今回はどんな場合に倒置が起こり、どんな語順に倒置するのか、正しい知識を身につけることで、倒置をマスターしましょう!
なぜ倒置をするのか
倒置された文章は本来、倒置しなくても意味は通る文章なんです。
たとえば、Here comes the king. という文章、The king comes here. でも意味は通じるし、他の文章でもそうなっているんです。
それなのに倒置に慣れてないと文構造がわかりづらくなり、意味を取るのが難しく感じてしまいますよね。
そんなややこしいことをどうして敢えてするのかというと、強調して聞き手の注意を引きたいからなんです。
だから文の語順を少し変えること、また強調したいことを文頭に置くことで相手の気を引こうということです。
英語話者が「conclusion comes first(結論から述べる)」という話し方をするように、彼らは一番大事な情報は最初にもってこようとする話し方をするため、倒置をするようです。
例外としては、主語を強調したいときです。
後ほどこのブログでも扱いますが、主語は通常文頭に置かれるものなのでこのときは主語を最後に置くことで強調します。
詳しくは後ほど紹介するのでぜひ最後まで読んでくださいね!
どんな法則で倒置が起こる?
否定語が文頭に置かれたとき
否定語、つまり否定を表す副詞(句、節)が文頭にきたとき、後ろの節が疑問文の形になります。
よって否定の副詞に続く文は、そのあとに続く主語+(助)動詞 が(助)動詞+主語 の語順になります。
では、ここで言う否定語とはどのようなものでしょうか?
☆代表的な否定語☆
never / hardly / scarcely / rarely / little / no /
noが入っている前置詞 / only / nor / not only but also / not
☆例文☆
Never have I seen such a perfect performance like this.
⇔ I have never seen such a perfect performance like this.
(これほど完璧な演技は見たことがない。)
Only this morning did I realize what was going on.
⇔ I realize what was going on only this morning.
(今朝になってやっと何が起こっているのかわかった。)
No sooner had John sat down than the phone rang.
⇔ The phone rang no sooner than John had sat down.
(ジョンが座ったとたん電話が鳴った。)
一番下の例で見られるような副詞句は直感的に文構造を捉えるのは一見難しそうですよね。
このような否定の副詞句、あるいは副詞節が文頭に置かれていたら要注意です!
長文で文構造を把握するのに時間をかけないように、ひと目で倒置が起こっていることを見抜けるように練習していきましょう。
so, nor, neither「…もそうである(ない)」
so, nor, neither を使い、前の文章を受けて、「…もそうである(ない)」と表すとき、倒置が起こり、so, nor, neither に続く形が疑問文の語順となります。
so+V S:直前に述べられた内容について「Sもまたそうだ」
neither[nor]+V S:直前に述べられた内容について「Sもまたそうでない」
では早速これらを使ってみましょう。
☆例文☆
⑴ I was born in Tokyo. - So was I.
⇔ I was born in Tokyo. – Me too.
(私は東京で生まれました。私もそうです。)
⑵ I don’t like this salad very much. – Nor do I.
⇔ I don’t like this salad very much. – Me, neither.
(このサラダはあんまり好きじゃないなぁ。わたしもそうです。)
⑶ The first one isn’t good and neither is the second.
⇔ Neither the first nor the second is good.
(最初のはよくないし、2番目のもよくない。)
⑷ I belong to the football team, and so does my brother.
⇔ I belong to the football team, and my brother does, too.
(私はそのフットボールチームに入っていて、兄もそうだ。)
⑸ We don’t want to go, and neither do they.
⇔ We don’t want to go. Nor do they.
(私達は行きたくないし、彼らもそうだ。)
ここでの注意点はnorとneitherの使い分けです。
neitherは副詞、norは接続詞なので⑶や⑸でみられたandのような接続詞の後にnor使うことはできません。
仮定法のifの省略
Ifを省略したとき、倒置が起こって疑問文の語順になります。
ただしifの仮定文ならなんでも倒置できる、ということではないのです!
ここにもちゃんと規則性があるので安心してくださいね。ifの省略によっての倒置は、以下の3パターンのみなんです!
(ちなみにこの倒置は文語で使われるパターンであり、基本的には会話ではほとんど使われません。)
be動詞(were)がある時
had + 過去分詞 がある時
shouldがあるとき
この3パターンのいずれかに俗していないと、ifの省略による倒置は起きません。
この3つの仮定文を倒置で書き換える場合は、⑴~⑶それぞれのbe動詞(were)・had + 過去分詞・shouldのそれぞれを文頭に出して、それぞれに続くように疑問文の形に変えればいいだけなんです。
それでは実際にどんな風に使われるのか見ていきましょう!
☆例文☆
Were I in your shoes, I would decline the offer.
⇔ If I were in your shoes, I would decline the offer.
(もし君の立場だったらその申し出を断るだろうね。)
Had he known the fact, he would have acted differently.
⇔ If he had known the fact, he would have acted differently.
(もし彼がその事実を知っていたら違った振る舞いをしていただろうに。)
Should you see him, please tell it to him.
⇔ If you should see him, please tell it to him.
(もし彼に会ったら彼にそれを伝えておいてね。)
どうでしたか?とっても簡単そうですよね!
そうなんです、倒置はルールさえ覚えてしまえば怖くはないんです。
とはいえやはり油断はできないんです。
それはズバリ、出題形式に隠されているのです。
先ほどは、ifのある仮定文から自分で省略した文章をつくる、という流れでしたが、この倒置が長文読解の問題で現れたときはどうでしょうか?
多くの出題ではifの省略された状態の文、例文の1行目の状態で文章中に紛れ込んでいるのです。
つまり、ifが隠されている文章であっても、倒置が起こっていることに気付き、仮定の意味を汲み取れているのか試されるのです。
やはり、こちらも長文に備えてこっそりifが省略された仮定文を見抜けるようにしておかないと、油断はできません。
場所の副詞(句)が文頭に置かれたとき
場所の副詞(句)が文頭に置かれたとき、倒置が起き、文頭の副詞(句)以下が疑問文の語順になります。
このとき、倒置することによって文頭の副詞(句)に続く名詞を強調しています。
☆例文☆
Here comes the bus.
⇔ The bus comes here.
(ほら、バスが来るよ。)
In my bag was his textbook.
⇔ His textbook was in my bag.
(私のバッグの中にあったのは彼の教科書だった。)
Near my house is the bank.
⇔ The bank is near my house.
(私の家のすぐそばにあるのがその銀行です。)
ここまでが長文で頻出するの倒置です!
以上の4つの用法は最低限押さえておきましょう。
ここからはたまにお目にかかるその他の場合の倒置です。
頻出ではありませんが登場したときに倒置をすぐに見抜いて対応できるように勉強していきましょう。
so … that~構文の場合
so … that~構文「~するほど…である」のso+形容詞(副詞)が強調のために文頭に置かれることがあり、その場合、主節(soに続く文節)の主語と動詞が疑問文と同じ形をとる倒置が起こります。
これはso以下の形容詞を強調するために倒置が起こっています。
☆例文☆
So angry was he that he posted the claim on the internet.
⇔ He was so angry that he posted the claim on the internet.
(彼はその文句をネットに書き込むほど怒っていた。)
So proud was she of the ring that she showed it to everyone she met.
⇔ She was so proud of the ring that she showed it to everyone she met.
(彼女は会った人みんなに見せびらかすほどその指輪を誇りに思っていた。)
形容詞+as+S V「~だけれども」
接続詞としてのasは〈~のとき、~なので、~ように、~につれて、~だけれども〉など多くの意味を持ちますが、ここでのasは〈だけれども〉の意味として取るときに限った用法です。
このとき、SVCのCにあたる形容詞が文頭に出され、倒置となります。それでは使い方を見ていきましょう。
☆例文☆
Young as she is, she has a strong sense of responsibility.
⇔ She has a strong sense of responsibility as she is young.
(彼女は若いのに責任感が強い。)
Reliable as it may look, it was a fake.
⇔ It was a fake as it may look reliable.
(信頼性がありそうだが、それは偽物だ。)
C+V+S 主語の強調
この場合は、第2文型(S V C)の文が、直前の文や節と関係のある補語が文頭に置かれ、また強調したい主語や長い主語が文末に持ってくることで、C V Sの語順となり、倒置になります。
このブログの冒頭で、強調したいことや新しい情報を英語話者は最初に持ってくる傾向にあると言いました。
しかし、文脈上最後に持ってくるほうが聞き手に伝わりやすい場合もあります。
それが今回のポイントです。
次の文章を比較してみましょう。
A「右手に見えますのが金閣寺でございます。」
B「金閣寺が右手に見えます。」
バスの中で乗務員がこのように言ったとします。Bだと「金閣寺」という主語が最初にくる通常通りの形になるので、なんだか平坦に聞こえる一方、Aのほうが通常の語順を変えることで乗客の目線を右に映してから「金閣寺」の情報を与えるので、臨場感があり、聞き手に伝わりやすくなります。
このような場合は、強調したいものを最後に持ってくることで強調しています。
☆例文☆
What you say is important, but more important is how you say it.
⇔ What you say is important, but how you say it is more important.
(何を言うかも大事だが、もっと大事なのはそれをどう言うかである。)
Happy is the man who knows his business.
⇔ The man who knows his business is happy.
(幸せなのは自分が何をすべきかわかっている人だ。)
ちなみに、CVSの形に倒置できるのに、何故OVSにならないの?と思った方もいるかもしれません。
そんなあなたのために、SVOの文章をOVSに倒置したらどうなるか検証してみましょう。
A cat chased Tom.
(ネコがトムを追いかけた)
↓
Tom chased a cat.
(トムが猫を追いかけた)
となり、意味が全くことなる別な文章が出来上がってしまい、SVOの文の形に戻ってしまうのです。
CVSの場合、普段はCにあたる形容詞が主語になることはないので、倒置が起こっていることを聞き手が把握することができるのですが、Oにあたる名詞を主語にしたところで、普段通りの文構造のままなので聞き手には倒置が起こっているかどうかの判別をつけることができなくなるのです。
まとめ
さて今回はいかがでしたか?
倒置は規則性さえ押さえ、理解すれば文構造を掴めずに混乱してしまったり、読み解くのに時間をかけてしまうこともなくなります。
長文でのつまずきや書き換えで悩む時間をこれで解消出来るのではないでしょうか。
①否定語が文頭に置かれたとき
②so, nor, neither「…もそうである(ない)」
③仮定法のifの省略
④場所の副詞(句)が文頭に置かれたとき
⑤so … that~構文の場合
⑥形容詞+as+S V「~だけれども」
⑦C+V+S 主語の強調
以上の規則性のもとで倒置が起こります。
倒置、と分かってしまえば主語と動詞を入れ替えて読みとけばいいのですが、倒置かもしれない!と疑うには訓練が必要です。
長文を読み解く中で詰まったら倒置じゃないか?と思わせるように強調して読みましょう。

札幌育ちの学生フリーランス。普段は英語科の大学に通い、オールイングリッシュの授業でネイティブから指導を受ける。主にウェブライターとして活動し、引きこもりながら細々と生活を送る。その反面、英語のスピーチコンテストをはじめ、ディベートやディスカッション、ポエトリーや英語劇など在学中に数々の大会に参加し、奮闘の末に受賞を果たす。スピーチ原稿を書いているときに、より多くの人自分の知識や価値観をシェアハピしたいと思い、ライターとしての活動を始める。

I took a Bachelor of Science degree in Mathematics where my problem-solving and critical-thinking skills were honed. I have worked as a trainer in a government office, which has helped me to develop my communication and intrapersonal skills. My hobbies are reading, listening to music, and cooking. After joining NativeCamp, I acquired 2 years of teaching experience. Currently, I am involved in content production in the Editing Department.