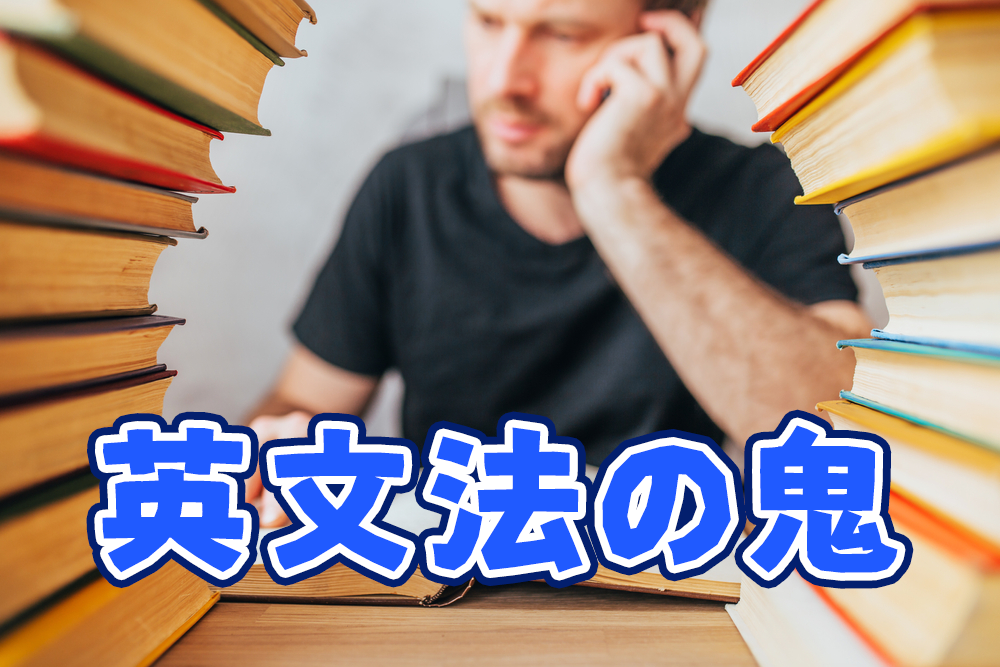
「自然な英語を話したい」「ネイティブスピーカーに近づきたい」
英語学習しているなかでそうした願いを胸に抱いたことがある人は、多いのではないでしょうか。では、どうすればそこに近づくことができると思いますか?
完璧な発音でしょうか。毎日英語のニュースを聞くことでしょうか。それとも、ディクテーションやシャドーイングなどの学習を続けることでしょうか。
2019年、「文法」という切り口から「ネイティブスピーカー感覚の文を書ける・話せる」を目指す書籍が出版されました。その名も『英文法の鬼100則』。「認知言語学」に基づいて解説されているというユニークさもあり、2020年には英文法書として売り上げNo.1に輝きました。今回は、この『英文法の鬼100則』について掘り下げていきます。
認知言語学習に基づいているとはどういうことなのか、この本から何が学べるのか、口コミを交えながら紹介します。それでは早速、書籍の概要から見ていきましょう!
- 英文法の丸暗記は必要ない?「伝わる英語」の秘密とは
- 日本語が見ている世界と英語が見ている世界の違い
- 可算名詞と不可算名詞
- 『英文法の鬼100則』の使い方
- 『英文法の鬼100則』はこんな人におすすめ
- 『英文法の鬼100則』まとめ
英文法の丸暗記は必要ない?「伝わる英語」の秘密とは
『英文法の鬼100則』、なんだか怖そうなタイトルですね。実はこの本は、明日香出版社が出している「鬼100則シリーズ」の中の1冊です。「鬼100則シリーズ」は、その迫力のあるタイトルとはうらはらに、「読みやすい」「よくわかる」「すぐに使える」をコンセプトとしています。
英語などの語学系参考書の他、「転職」「接客」「株」などのビジネス書も展開しているので、どこかで目にしたことがある方もいるかもしれませんね。
『英文法の鬼100則』もそのシリーズ名に恥じない内容となっています。
英語を学習していてぶつかる「なんでそうなるんだろう?」という疑問に対して、わかりやすい解説や見やすいデザイン、理解を助けてくれるイラストなどで「相手にしっかり伝わる英語」が使えるように、と導いてくれます。
そして、「伝わる英語」に必要なのは「文法の丸暗記ではない」と、受験英語を一刀両断。大切なのは「英語の気持ちと型を理解すること」という斬新な切り口をベースに英文法100項がまとめられています。
英語の気持ちを理解するには、英語が見ている世界を理解しなければなりません。はたして、英語が見ている世界は日本語が見ている世界とどのように違うのでしょうか。
日本語が見ている世界と英語が見ている世界の違い
『英文法の鬼100則』は、「認知言語学」に基づいた文法解説が斬新だということで話題になりました。「認知言語学」とはつまり、その言語がどのように世界を認知しているか、その言語が見ている世界はどのようなものなのか、そういう側面から言語を捉えよう、という学問です。
「ここはどこ?」と「私はどこ?」
本の冒頭で、まず、日本語と英語での世界の捉え方(認知の仕方)の違いは、見ている世界に話者が登場しているか、していないか、だと解説されます。例文として出されているのは「ここはどこ?」という表現です。この日本語を、英語に置き換えた場合、どうなると思いますか?直訳すると
Where is here?
ですよね。この英文は、一見合っているようですが、実は自然な英語ではありません。
「ここはどこ?」を英語で表現する場合、以下の言い回しになるのです。
Where am I?
日本語に直訳すると「私はどこにいますか?」ですね。「ここはどこ?」と「私はどこ?」の違いは、日本語と英語が見ている「世界の違い」です。
日本語は「自分がカメラになって外の世界を眺める」言語、すなわち、見ている世界に自分の姿はありません。そこには景色しかないのです。その結果、「ここはどこ?」と、景色についてたずねる文となります。
一方、英語は「外からもうひとりの自分が自分を眺めている」言語です。つまり、英語が見ている世界には自分自身が登場しているので、幽体離脱的な世界だともいえます。見ている世界に「自分」がいるので、「私は今どこに立っているのか?」と、「私(自分)」が主語となるのです。
「ここはどこ?」の他にも例が紹介されています。
「家はからっぽ」と「私はその家が空であることを見つけた」
「〇〇は~だったよ」という内容の文章、日本語では〇〇が主語になりますが、英語の場合はI found 〇〇 ~.
という表現の方が「英語らしい英語」に聞こえます。
例として、友人宅へ遊びに行っても誰もいなかった、というシチュエーションでの表現を見てみましょう。
家は空っぽだったよ。
◎ I found the house empty.
日本語では自分が見ている景色の中にある「家」が主語ですが、英語の場合はその家を見ている「自分」が主語になり得るのです。
英語学習をしていて「英語ってまわりくどいな!」「自分が自分がって主語の主張がはげしいな!」と違和感を感じたことが何度となくありますが、その背景には、こうした「見ている世界の違い」があると知り、納得です。
可算名詞と不可算名詞
数えられる名詞と数えられない名詞。単語ごとにどちらに属するか暗記をして試験に臨んでいた学生時代を思い出す文法事項です。ところがこの可算・不可算名詞についても、見ている世界の違いを理解すれば暗記の必要はないのです。『英文法の鬼100則』では、「5歳以上の人類なら誰でもわかる」と、その理由を解説しています。
人間は、5歳ぐらいになると2つの見方で世界を捉えます。
② 「材質・素材」で認識する
どういうことかというと、①は形がくずれたら「それ」とはよべないもの、たとえば「机」「いす」などです。「机」を粉々にして、その姿をみても、「これは机だ」とは思わないでしょう。このように、形がくずれてしまったら別のものになってしまう、そう認識されているものはパターン①です。
一方、②は形に関係なく認識できるものです。
例えば氷は砕いても氷です。ガラスも粉々になったとしてもガラスです。ちぎられてもパンはパンだし、折れてもチョークはチョークです。このように、いくら形をくずしても「それ」だといえるものが認識パターン②に属します。
英語の世界では、「何個」と数えられるものは①のパターン、形で認識できるものだけ。②のパターンは数えられません。これが、英語が見ている世界においての数えられるもの(可算名詞)と数えられないもの(不可算名詞)の違いなのです。
なにしろ100則あるので、ここですべてを紹介することはできませんが、このように「英語はどのように世界を見ているのか」を知ることで英文法の理解が深まる、なんとなく感じていた違和感が解き明かされる、そんな文法解説書が『英文法の鬼100則』なのです。
『英文法の鬼100則』の使い方
ここでは『英文法の鬼100則』の構成について紹介します。まず、「文法が100項目もあるのか…」「440ページって多くない?」と、そのボリューム感にひるんでしまう方がいるかもしれません。
けれどもこちらの本は「1つの項目が見開きx2(全4ページ)にまとめられている」というシンプル構成なので、実はそれほどとっつきにくさは感じさせません。興味のある項目や、確認したい文法事項のところだけ開いて目を通す、ということも容易です。
たとえば、教科書との併用もおすすめです。予習や復習の際に教科書プラスアルファとしてこの本の該当項目に目を通す、という使い方をすれば、より理解が深まることでしょう。
見開きでまとめられているので、毎晩1項目ずつ読み進めるぞ!といったコツコツ学習にも向いています。電子書籍でも読みやすいつくりなので、通勤・通学のおともにもピッタリ。
見開きのどこかにはイラストが入っているので、そのイメージと共に学習内容が頭にすっと入ってくるのも、学習者にはありがたいですよね。
本全体の内容的な構成は、100則のうち91則が「書くため・話すため」の英文法解説。これは、先ほど例えとして紹介した「英語の気持ちを知る」「英語が見ている世界を知る」観点から文法解説されている部分です。
92~100則は、「人を説得するための英語」を書いたり話したりするための「型」の解説。レポート作成やプレゼンの原稿づくりなどで実践できる内容となっています。
そうはいっても受験勉強や資格試験に最強なのは丸暗記でしょう!と思う方がいるかもしれませんが、「人を説得するための英語」はライティングやスピーキングのテストにも効果的。エッセイライティングの型は資格試験でも使える万能な型なのです。
また、英語のために習得した「型」は、日本語で話すときにも応用できますので、日常生活でも変化を実感できるかもしれませんね!
『英文法の鬼100則』はこんな人におすすめ
この本を読んだ人の感想には、以下のようなものがあります。・学生時代になんとなく覚えていた文法の背景を知ることができた
・英語への理解が深まった
・これまでの文法学習で腑に落ちなかったニュアンスの違いがわかった
・今までこんな説明聞いたことがなかった!わくわくして楽しい!
文法について専門用語を多用することなく解説してあるので、文法書というよりは、読み物として「目からうろこ!」と楽しんでいるうちに、英語の世界に対する理解が深まっている様子が伝わってきますね。
こうした感想からもわかるように、この本は以下の方におすすめです。
・自然な表現を学びたい
・丸暗記に頼らず英語力をUPしたい
・目からうろこ体験をしたい
・英語が好きなので興味を持って解説を読める
・学生時代、英語は丸暗記でのりきったけどこのままじゃいけない!と思っている
逆に言えば、次のような方にはあまり向いていないかもしれません。
・概念で説明されるのが苦手
・英語レベルが超初級者
あまり自分には向いていないかも、と感じた方でも、この本を読んで得られる「目からうろこ」感は気持ちが良いので、機会があったら手に取っていただけると嬉しいです!
『英文法の鬼100則』まとめ
今回は、切り口が新しい文法書、『英文法の鬼100則』について見てきました。英文法は丸暗記をしなくても、なぜそういう文法になっているのかを理解することで身につけることが可能です。
そのことを理解するポイントは、「英語が見ている世界」を知ることにあります。
そういう考えに基づいて英文法が解説されている『英文法の鬼100則』は、1則が見開きx2(4ページ)にまとめられているなど、学習しやすい工夫も満載。
英文法は暗記でのりきってきたという方も、英語の理解を深めたいという方も、『英文法の鬼100則』を通じて「英語で見る世界」を手に入れて、自然な英語を紡いでいきましょう!

東京在住、元IT系で今は2児の母業に専念中。パッキング作業が大の苦手なのに数年に1回海外引越する生活が続き、日本に落ち着いた今でもたまに夢の中で荷造りしている。渡った先は欧州、南米、オセアニア…人生通算で一番長く住んだのは英国。中でもロンドンでモノクロフォトグラフィーにはまり暗室にこもっていた頃が一番の思い出。趣味はカメラとミシンと鉱物収集。形から入る派なのでモノが増えがち。ミニマリストな生活が夢。

I took a Bachelor of Science degree in Mathematics where my problem-solving and critical-thinking skills were honed. I have worked as a trainer in a government office, which has helped me to develop my communication and intrapersonal skills. My hobbies are reading, listening to music, and cooking. After joining NativeCamp, I acquired 2 years of teaching experience. Currently, I am involved in content production in the Editing Department.




