
「中国語の発音は難しい。」こうした声を聞いたことはありますか?
外国語を学ぶ人が最初にぶつかる壁は発音かもしれません。発音を勉強するために初級の学習本を購入される方もおられるでしょう。
他言語の発音が難しい理由の一つは日本語にはない口や舌の使い方があるという点です。
今回は、日本人が特に難しく感じる音に注目して発音のコツをご紹介したいと思います。
- 子音の音声は短い
- 子音に濁音という概念はない
- 子音だけで練習せず母音を入れて練習してみよう
- 有気音と無気音を区別する
- 有気音と無気音はどちらも破裂音
- 息を出すタイミングを変える気音トレーニング
- 舌と唇の使い方が重要
- 舌の形と位置
- 声調パターンを身につける勉強法で子音と母音をトータルトレーニング
- まとめ
子音の音声は短い
日本語でも一つの音は子音と母音で構成されていることにお気づきかもしれません。
例えば「か」ですと、kとaという、子音+母音に分けることができます。「か」を発音しようとすると、口の奥で舌を使って閉鎖状態を作り、息をそこで破裂させることで発音しているのです。この閉鎖から破裂までの流れがkという音を生み出しています。
この音だけとってみても、子音の音はとても短く、パッと息を出したような感じに聞こえることでしょう。他の子音もそうですが、子音は母音と比べて単独では意味を成さず、しかも短く聞こえる音なのです。それでもどうでもいいというわけではなく、子音を正確に伝えないとはっきりと音が聞き取れないので発音を学ぶ際は発音方法に注意する必要があります。
子音に濁音という概念はない
濁音というのは簡単に言うと平仮名の右上に2つの点を加えた言葉です。
例えば、がぎぐげご、というような言葉です。日本語ではこれを、かきくけこ、と対比させて学習します。それだけ濁音の有無は音の違いにつながるほど重要なのです。
しかし中国語は濁音という考えはありません。
中国語初級の本では濁音のように発音して中国語の無気音を発音しましょう、というような説明を見かけることもありますが、濁音字体の概念がないので、濁音で発音すると、日本人の耳からするとそれっぽく聞こえるとしても、やはりネイティブの発音とは違って聞こえます。
濁音というのは最初から終わりまで声帯の振動があります。中国語ももちろん声帯の振動はありますが、中国語初心者の方は濁音で発音することを学ぶよりも、これから解説する息の使い方を学習するほうが発音のコツをつかみやすいことでしょう。
子音だけで練習せず母音を入れて練習してみよう
息の使い方は中国語でとても大事な部分です。
息の使い方で言葉の意味が変わるといっても過言ではありません。
それでも子音で学んだ息の出し方を定着させるには、子音だけでは不十分です。
日本語でも子音+母音で始めて一つの音ができるように、中国語でも、単語や漢字で表現できるような単位で発音するほうがはるかに実用的でしょう。
つまり必ず母音を入れて発音するということです。
しかしこれだけでは漢字になりません。
なぜなら中国語には四声というものがあり、音の上げ下げなどのイントネーションの違いも含まれるからです。
ここまでを理解しながら漢字を丁寧に読む練習を積むことで実践的な訓練をすることができます。
有気音と無気音を区別する
息の出し方が中国語には重要ということは伝えましたが、どれほど重要なのでしょうか?
これには有気音と無気音という観点で説明する必要があります。
有気音と無気音という言葉から、一つは息を出す、もう一つは息を出さないと思いがちですが、そうではありません。
息は無気音でも出ます。もっというと、息のない音は存在しません。音を出すときには必ず息が必要なのです。
では息をどのように区別して使えば有気音と無気音が出せるのでしょうか?
まず、有気音と無気音の違いは、poとbo、 deと teなど、p(有気音)とb(無気音)、t(有気音)とd(無気音)の中国語の音の違いを指しています。
このアルファベットを日本語っぽく発音しようとすると、bの発音のときに濁音を入れがちですが、そうではなくpとbの舌の位置や口の中の形は基本的に同じだということに注意して下さい。
有気音と無気音はどちらも破裂音
pとbの音を作る場所は唇の上下を合わせた所で発生します。
日本語で表記するとどちらも唇の閉鎖から息の開放なので、「パッ」と聞こえるかもしれません。
つまりどちらも破裂音ということです。
それでは破裂の大きさが有気音と無気音の違いなのでしょうか。
音声を聞くと有気音のほうが息がたくさん出ているように聞こえるので破裂の大きさの違いのように感じられますが、本当はその後の部分が重要なのです。
つまり唇の閉鎖から開放した後の息の長さがポイントなのです。
息が長いほど息がたくさん出ているように感じ、息が短いほど無気音に聞こえるのです。
では息の長さを具体的にどのように変えたらいいのでしょうか。息を出すタイミングについて考えてみましょう。
息を出すタイミングを変える気音トレーニング
息を出すタイミングですが、先ほどのpとbを例にすると、閉鎖から開放したときにまず息が勢いよく出て、その後に母音が続きます。
この母音が現れるまでの息の長さが有気音と無気音を区別する鍵なのです。
有気音のpoだとp+息+oとなり、oが遅れて出ることで息がはっきりと聞こえ、有気音だと判別できます。
無気音boでは、b+o(息と音がほぼ同時)になり、息があまり聞こえないのです。
こうした違いを意識して母音を入れた子音bo、 po、 zi、 ci、 zhi、 chi、 ge、 ke、 de、 teなどを有気音と無気音区別させながら発音練習してみるのはどうでしょうか。
四声を取り入れると、より実践的なのですが、四声に慣れないうちはやりやすい第一声(高く平らに伸ばす)の声調にして練習すればいいかもしれません。
焦らずこつこつと練習してみましょう。練習していくうちに息を出すタイミングをつかみやすくなるでしょう。
こうした方法で有気音と無気音を確実にマスターできるでしょう
舌と唇の使い方が重要
子音は特に舌の位置や使い方(舌を上顎や歯茎にどのように当てるのか)そして唇をよく使います。
唇を使う音(唇音)は、子音b p m fがあります。唇を使った子音は日本人にとってそんなに難しくありません。
あえて言うならfは唇と上の前歯を使った音なので注意しましょう。他のbpmは両唇を使います。
ここで少し余談!
下記記事では、同じ漢字なのに違う意味を持つ中国語について解説しています!いざ使う場面になって、混乱しないように正しい使い方をマスターしていきましょう♪♪
舌の形と位置
舌をどこにおいて(または当てて)発音するかがポイントです。
この舌の使い方で、舌尖音、舌根音、舌歯音、そり舌音、舌面音と様々な音を出すことができます。
この5種類の中でさらに有気音と無気音また摩擦音(舌をおいた場所に息を通して摩擦させて作り出す音)、振動音(舌を振動させる)に分類できます。
これから日本人が苦手な子音に絞って解説していきます。
① 舌根音(ge ke he)
ポイントは喉をこすること
gkhの子音の発音するポイントは喉の声帯あたりを使います。
ここで閉鎖状態から息の開放(gとk)、または息を勢いよく通すことでhの音を作り出します。
日本語では「はー」と言っても口の中での摩擦なのでさらに奥を意識して発音しなければなりません。
練習のときは多少おかしく聞こえても息が喉を勢いよく擦るイメージで子音を発音してみて下さい。練習していくうちに喉を息が擦る感覚が身についてくるでしょう。
② 舌尖音(de,te ne le)
ポイントは舌先を歯茎に当てること
この子音は舌先を必ず使います。特に苦手とする音はleかもしれません。英語でもrとlの音を苦手とする方も多くいらっしゃることでしょう。
中国語のlですが、ポイントは上の前歯の裏と歯茎の境目、または歯茎あたりに舌先を当てます。この際舌先をしっかり押し当てないようにして下さい。なぜならlの音は舌先を当てた部分ではなく、当てていない舌の両側のサイドで息を感じることがポイントだからです。
練習としては鏡を使ってでもいいので舌先を歯茎に当てるようにして、両側で音が響く感覚を養うように練習しましょう。両側の響きを感じるようになったらこの音もすぐにマスターできることでしょう。
③ 舌歯音(zi ci si)
ポイントは舌先を前歯に当てること
この音も舌先を使う音です。今度は舌先を前歯の裏に当てて下さい。力を入れて押し当てる必要はありません。
舌の先が歯の裏にあたって空気の閉鎖状態を作り出せば、息のタイミングで無気音のziと有気音のciを発音できます。
ポイントは舌の先端を意識することです。
zとcの音に続く母音iは単独の母音iとは異なります。舌先を使う子音の影響を受けているので舌先の音の響きがないと正確なziやciを出せません。
舌の先端の音の響きを感じられるならば音をそこに通して摩擦させる音siもすぐにマスターできることでしょう。
④ そり舌音(zhi chi shi ri)
ポイントは舌の奥を上顎に当てること
この音は舌先ではなく、舌の奥(だいたい真ん中辺り)を使います。イメージとしては舌の奥の面を上顎に当てる感覚です。
この発音をマスターするために人によってイメージのわかりやすい音とわかりにくい音があることを覚えておくといいかもしれません。
オススメなのは比較的イメージしやすい音shiを先に練習してみる方法です。
この音は有気音と無気音ではなく、摩擦音なので、舌の真ん中で閉鎖状態を作る必要はありません。
ただ舌の奥を上顎に押し当てますが、完全に塞ぐのではなく息を通す部分を残すことで摩擦させるようにします。子の音は日本語の「し」とも違ったこもった音です。
何度も練習して摩擦させたときの音の感覚をマスターしましょう。
この摩擦音が分かれば、その舌を今度は振動させます。日本語の「り」に濁音をつけたような感覚です。
shiの音をマスターした後なので、比較的難しくないことでしょう。舌の形はshiの形をキープしてただ舌を振動させたらそれで完璧です。
中国語の中では少ない振動音をマスターできたら後はzhiとchiの練習です。
shiのときの隙間を塞いで閉鎖状態にして息を開放できるようになれば、zhiとchiの発音は簡単にマスターできます。
後は息を出すタイミングを変えることで有気音chiと無気音のzhiをすることができます。
声調パターンを身につける勉強法で子音と母音をトータルトレーニング
子音の発音練習には母音が不可欠です。それに加えて四声を入れて練習すればより実践的な練習になります。特に四声の組み合わせを変えた漢字二文字の単語を練習してみるのはどうでしょうか。
四声をそれぞれ変えた漢字二文字の単語の例)
飞机(fei1 ji1):飛行機
家庭(jia1 ting2):家庭
修理(xiu1 li3):修理
音乐(yin1 yue4):音楽
まとめ
四声と母音、子音を正確にマスターして初めて通じる単語を話すことができます。
やるべきことは多いように感じますが、四声などをパターン化して、息を出すタイミングといった子音の発音のコツを意識しながら反復練習をすることで確実に努力が実ることでしょう。
諦めず続けるなら発音マスターも夢ではありません。
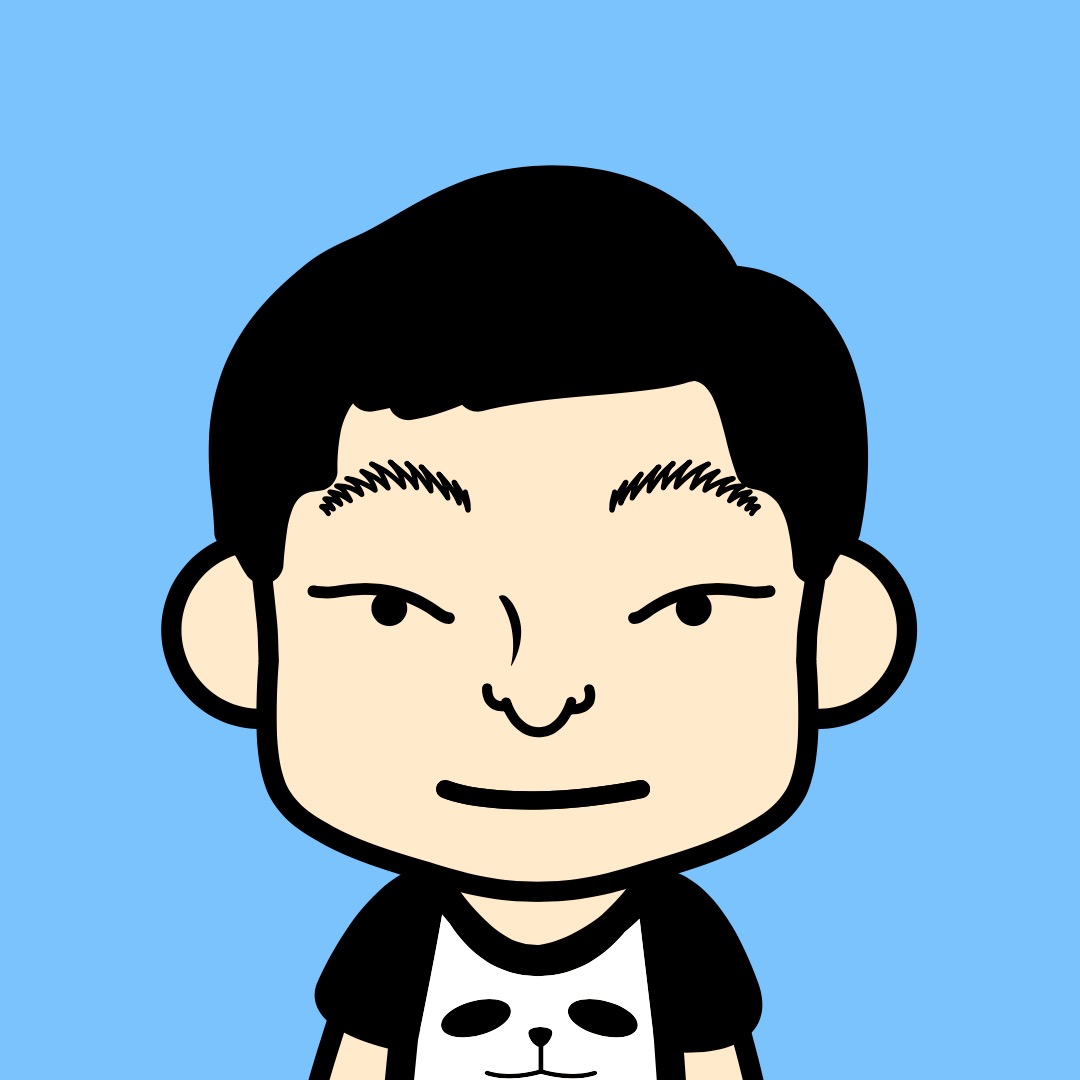
中国語講師として様々な方に基礎から指導してきました。 文法解説や発音指導、フレキシブルなレッスン時間の点で、よい評判もいただいております。 中国語能力を測る資格試験、HSKの最上位6級にも合格しています。(中国語の新聞、ドラマを見たり聞いて理解可能なレベル) もし中国語にご関心があればスカイプ及びLINEより中国語を教えることができます。(30分:500円から) ご連絡は下記のブログからお待ちしております。 https://chinesekun.hatenablog.com/




