
英語を習う上で外せないのが「使役動詞」。名前を見てもあまりどういうものかピンとこないかもしれません。
ここでは、そんな使役動詞の紹介と、それぞれの使い方・使い分けを例文込みで解説していきます。
高校で習うレベルですが、英会話となるとしっかり定着していなければすぐに出てこない文法です。何度も反復して、その使い方を脳に焼き付けていきましょう。
使役動詞とその種類
そもそも使役動詞とは何か、どれだけの種類があるのか、それについてまず理解しておきましょう。使役動詞とは、和訳すれば「人やものに~させる」または「人やものに~してもらう」という意味を持つ動詞のことです。この意味を持つものは4種類あり、have / make / let / getを伝えたい事柄によって使い分けます。厳密に言えばgetは使役動詞ではないのですが、同じ意味として使われるためここでは使役動詞の種類の1つとしてカウントすることとします。
使役動詞haveの使い方
使役動詞とその種類がわかったところで、次はその使い分けについて学んでいきましょう。まずはhaveからです。使役動詞のhaveは、「~してもらう」と訳すことが多いです。使役動詞の訳は、上記でも述べたように「人やものに~させる」または「人やものに~してもらう」となるのですが、これは基本であり、伝えたいことやそのニュアンスが異なれば和訳もそれに対応しなければ違和感があります。直訳よりも意訳の方がしっくりくる場合には少し言い方を変えてみましょう。
覚えるべき公式は「have + 目的語 + 原型不定詞(do)」です。これを使った例文とその訳を見てみましょう。
「自転車を壊してしまったので、父に直してもらった。」
パッと見た感じどうでしょうか。高校の英文法が定着していない場合、1文の中に2つも一般動詞があることに違和感を覚えるかもしれません。
中学英語では1文に動詞は基本的に2つ入れられないと習ったので、こちらが大きく作用しているのでしょう。けれど、使役動詞を学ぶならまずはこの形に慣れる必要があります。
また、こちらの訳は「直してもらった」としましたが、使役動詞の基本の訳は2種類ありましたから、もう一方の方で訳すと「直させた」となります。
しかし、これでは例文的には違和感のある印象で、父親より子どもの方が随分と偉そうです。このように、状況や文脈によって訳は伝えやすいように変えていくのがポイントです。
過去分詞を使った使役動詞haveの使い方
使役動詞のhaveは、過去分詞と一緒に使うとまた違う意味を持ちます。ここが厄介なので妥協してしまう人がいます。まず、覚えるべき公式は「have+目的語(人以外)+過去分詞(done)」なので、これをしっかり頭に叩き込みましょう。
そして、この公式が出てきた時には使役動詞のhaveは2つの意味を持ちます。元は使役の「~をしてもらう」という意味なので先ほど覚えましたよね。
追加されるのは、被害の意味を持つ「~を~される」という意味です。以下の例文で感覚を掴んでいきましょう。
「彼女は財布を盗まれた。」
この訳で「~してもらう」、「~させた」を使うと明らかにおかしな文章になってしまいますよね。「盗んでもらった」、「盗ませた」なんて訳は不自然です。
勘の良い人なら日本語訳を暗記していなくても文脈から正解に辿り着けるので、暗記に頼りすぎる必要はありません。意味が通るように推測する力があれば自然に伝わるものです。
使役動詞 makeの使い方
それでは次に、使役動詞makeの使い方を覚えていきましょう。公式は、「make+目的語+原型不定詞(do)」となります。こちらは使役動詞のhaveと違って、強制的な意味を含むため、基本的な訳は「~に(無理矢理)~させる」になります。さっそく例文を見ていきましょう。
「ブラウン先生は生徒たちにフランス語の本を読ませた。」
これなら、ちょっと言い方は悪いかもしれませんが、先生が生徒に対して何かを強制させることはありえるので強制の意味を持つmakeを使っても良いでしょう。
使役動詞としてmakeは明らかに変だという場合、例えば「お世話をしてもらって感謝している」のような場合では、「~してもらう」という意味を持つhaveの方を使います。でないと、世話を強制して感謝しているという変な文になってしまうからです。このように、意味を見て使役動詞を使い分けましょう。
受動態のmakeの使い方
使役動詞のmakeを学ぶ時、セットで着いてくるのが受動態のmakeの使い方です。この公式は「be動詞+made+to+動詞の原型(do)」で以下のように使い、変わらず使役動詞の強制の意味を持ちます。「私は母によって数学を勉強させられた。」
慣れないうちはやはり違和感がある語順かもしれませんが、一度慣れてしまえばいつでもパッと出てくるので練習してみてくださいね。
それから、makeには人以外に使う時に公式が変わることも忘れずに。「主語(もの・事)+make+目的語+原型不定詞(do)」という公式になり、意味は「~(もの・事)が原因で~は~する」となります。
これもただ読むだけであれば、わざわざ公式を覚えずともニュアンスで理解できる人もいますので、必ずしも暗記が必要とは思いません。
「そのうち強風が原因でこの屋根は壊れるだろう。」
この例文の訳は、より自然になるように使役動詞が持つ意味を持っていないかのようになっています。使役動詞が持つ訳で訳したものの、違和感のある文になってしまったというのであれば、意味の通る自然な文に変えてみましょう。
使役動詞 letの使い方
次は使役動詞letの使い方です。公式は「let+目的語+原型不定詞(do)」になります。使役動詞の中でも許可の意味を含んでいることが特徴で、基本的な訳は「~に~させる」です。これだと強制にも捉えられるので、和訳してしまうと見えなくなる意図に注意を払ってみましょう。
「もし子どもたちが宿題を終わらせたら、彼らに公園でサッカーをさせてやる。」
訳はこれと違うものでもOKです。少し上から目線な訳になっているので、許可を全面に押し出した訳でも良いでしょう。
使役動詞の中でもletを使うべきなのは、その人がしたいと思っていることに対してです。
例えば、上記の例文であれば子どもたちはサッカーを公園でしたいと思っていることがletを使う条件となります。逆に、したくもないことに対して使うのは違和感があるので、それなら別の使役動詞であるhaveを使う方が自然でしょう。
外国人が投稿している人気動画などでは、Let me check it. 「確認させてください。」といった表現もよく使われています。
「私に~させて」という意味で、letが文頭に来ることでカジュアルな日常会話で使える表現となっています。短い文ですし、何度も聞くと耳に残るのでそのまま丸覚えしてしまえるでしょう。
ここで少し余談!
下記記事では、英会話学習の最適な頻度についてご紹介しています!効率よく学習を進めるためにも、ぜひ参考にしてください♪♪
使役動詞 getの使い方
では最後に、使役動詞getの使い方を解説していきます。最初にgetは厳密には使役動詞ではないと言いましたが、それでも意味は使役になるので紹介します。公式は「get+目的語+to不定詞」で、意味は「~に~してもらう」、「~に~させる」です。これを見て、haveと同じではないかと思ったかもしれませんね。その通り、ほぼ同じ意味として使われます。
どちらでも良いという場合もあるので、正解を1つに絞りたがる日本人が作るテストではどちらかはっきりした方が使われます。語群があるなら、答えを1つにするためにgetかhave、どちらかはあえてそこにないでしょう。
「私はボーイフレンドに家まで送ってもらった。」
使役動詞のgetは結構万能で、文法的には使役動詞ではないにもかかわらず幅広い意味で使えます。しかし、意味がhaveと被っていることで少し覚えにくかったり、どちらを使った方が良いのか迷いやすいのが難点です。これらは基本的にどちらでも正解と覚えておき、あとは慣れで覚えていくのが確かでしょう。
ネイティブスピーカーだって意識的に使い分けているわけではありません。英文法を事細かに研究し、学問として先行している人なら例外ですが、そうでなければ日常生活でそう意識はしていません。だから、どのような場面でhaveを使い、どのような場面でletを使うのかを聞いて真似してみるのが一番です。
過去分詞を使った使役動詞getの使い方
使役動詞getは、haveと同じように過去分詞を使って文を作ることもできます。公式は「get+目的語(人以外)+過去分詞(done)」です。また意味は増え、使役の「~をしてもらう」の他に被害を表す「~を~される」、完了を表す「~を~してしまう」が追加されます。
使役は先ほどの例文通りの使い方、そして被害を表す使い方はhaveで見た通りです。そのhaveをgetに置き換えて同じように使えます。では、完了の使い方はどうなるのでしょうか。
「キャシーは期限までに宿題を終わらせることができなかった。」
完了と言えば、現在完了形の完了用法を思い出した人も多いのではないでしょうか。それ以外でもこのように表すことができるので覚えておきましょう。同じ意味でも、複数の言い回しを持っている人はネイティブスピーカーに近づけます。
私が使う日本語でも、あらゆる言い方があってそれを無意識に選択していますよね。どうして同じ意味に複数の言い回しがあるの!と覚えにくさにイライラするかもしれませんが、語学とはそういうものなのです。
ここでまた少し余談!
下記記事では、オンライン英会話のレベル別の学習法をご紹介しています!これからオンライン英会話に挑戦しようと思っている方も、現在挑戦している方も、ぜひ参考にしてみて下さい♪♪
まとめ
さて、これで4つの使役動詞の使い方を解説し終わりました。中には似た意味を持つものであったり、公式が微妙に違っていたり、意味が追加されてしまったりと、わかりにくいものもあったと思います。しかし、わかりにくいものだからこそ、それをマスターした時の達成感と成長率は大きいものでしょう。皆がつまづきやすいところを得意にすればかなり差を付けられるはずです。
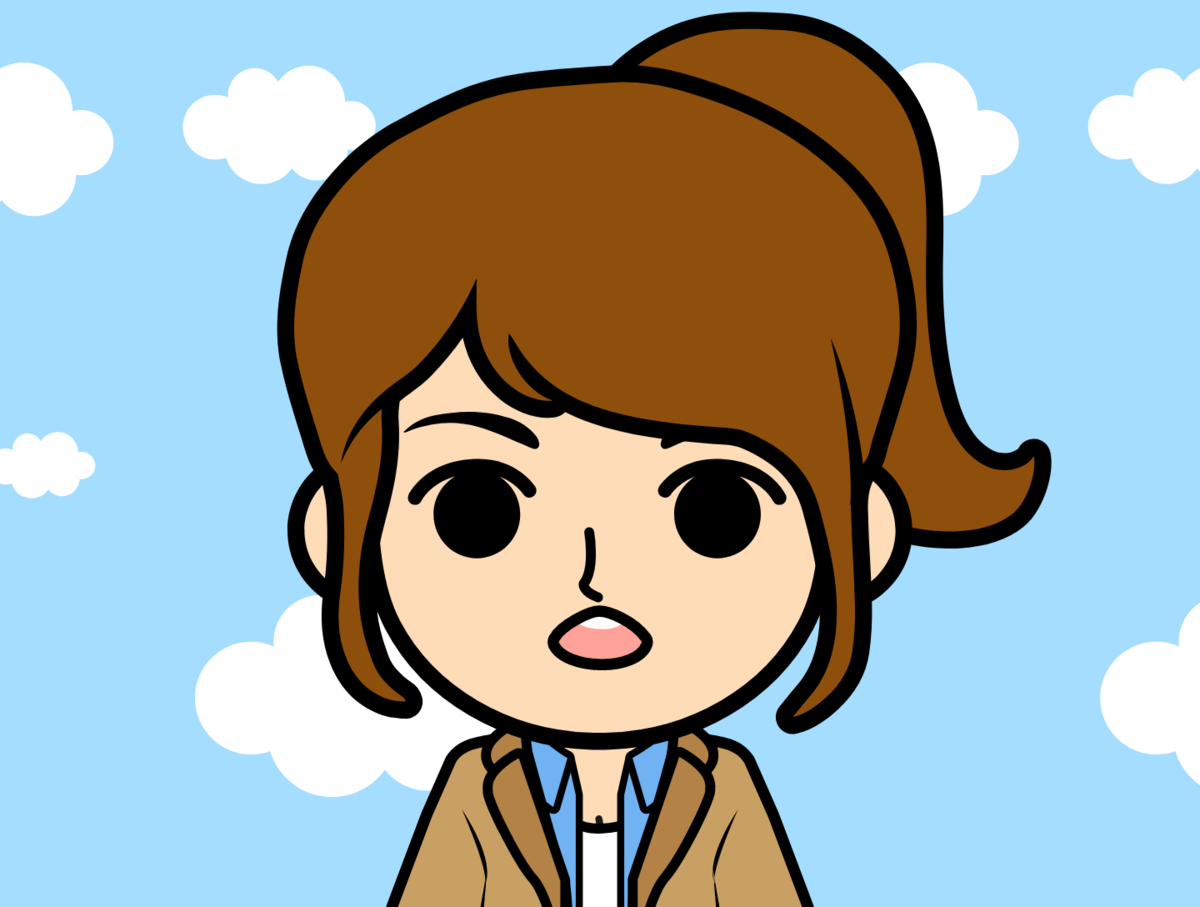
◇経歴
英語科高校卒
外国語学部英米学科卒
学習塾で英語を教えている
◇資格
・IELTS6.5
◇留学経験
イングランドのオックスフォードのOxford English Centreに3週間の語学留学と、スコットランドのエディンバラのUniversity of Edinburghに1年間の交換留学をしていました。
◇海外渡航経験
高校時代にオックスフォードの語学学校へ留学
大学時代にエディンバラ大学へ1年交換留学
◇自己紹介
ハリー・ポッターがきっかけで英語に目覚め、高校・大学とイギリスに留学したイギリスマニア。学校はアメリカ英語なので自己流でイギリス英語を習得。発音、スペル、すべてにおいてクイーンズ・イングリッシュを使い英語の先生にバツをくらうもめげず。生まれも育ちも日本で、海外に繋がりがなかったため留学が夢となった。アルバイトで全資金を稼ぎ渡英すると、勝手な高い理想を上回るほどの素晴らしさを目の当たりにし更に虜に。

I took a Bachelor of Science degree in Mathematics where my problem-solving and critical-thinking skills were honed. I have worked as a trainer in a government office, which has helped me to develop my communication and intrapersonal skills. My hobbies are reading, listening to music, and cooking. After joining NativeCamp, I acquired 2 years of teaching experience. Currently, I am involved in content production in the Editing Department.




