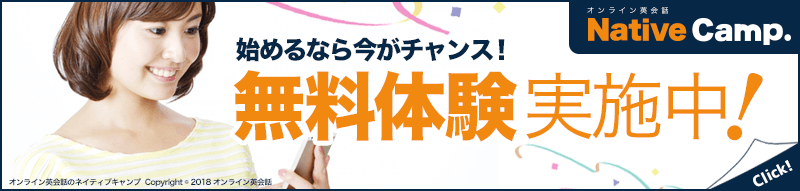今日のテーマは、語順です。
語順は、文型によって決まります。
文型をきちんと識別できることによって、英語という言語への扉が開かれるのです。基本5文型は、そうした文型の概念と役割を確認するための基本的となります。
理解に自信が持てるまできちんと取り組んでください。
では、本記事では「文型」とは何か、そして「基本5文型」の紹介とそれぞれの特徴を説明します。
また、文型を見分けるコツを紹介させていただきます!
1.文型とは何か?
英語での文型とはそもそも何でしょう。
それは、「英文」として認められるための条件です。
「文」は、「一区切りのまとまりのある考えを示すもの」(『大辞泉』)ですが、その「一区切り」の「条件」を示したものが文型で、述語の内容ごとに決められています
例えば loveが「愛している」という内容を伝える述語のときは、以下の2つが条件です。
1)「①愛しているのは誰か?」と「②愛されるのは誰か?」を示す。
2) ①は love の左、右に②を置く。
こうした条件は、学習用辞典のloveの項では、以下のように表記されます。
S V O(SがOを愛する)
注:SはSubject(「主題」など)のSで、簡単にいえば「文の主人公」のことです。
Oは、Object(「対象」)のOで、Vに表される行為(ここでは love)の「対象」に当たります。
Sがいなければ、「Oを愛する」という行為は生まれませんので、「文の主人公(=「文になくてはならない存在」)」というわけです。文型を扱う場合は、Sが「主語」、Oが「目的語」と訳されます。
こういうルールは、日本語にはありません。
その証拠に「愛している」とか「彼女を愛している」で文を終えても、「文がおかしい」とは言われません。
しかし英語では違います。
「彼女を愛している」を “Her love.”としても、伝えたい内容は伝わりません。
愛しているのは誰か、愛されているのは誰か、という情報が、指定の位置に置かれてはじめて内容が伝わります。
そしてここではじめて、様々な文法チェックが必要となります。
例えば英語には主格の形や3人称単数の主語につく動詞に -s がつくといった形式上のルールがありますが、“Her love.”を “Her loves.”と訂正しても何の意味もありません。
文型に則って正しい語順に単語が並べられてはじめて、文法チェックができるのです。
冒頭で述べた、文型が英文法のなかで最も重要とはそういう意味です。
2.基本5文型の紹介!
以下が、基本5文型のラインナップです。
Ⅰ) S V Ⅱ) S V C Ⅲ) S V O Ⅳ) S V O O Ⅴ) S V O C
すでに書いたように、これらは、数ある文型の中から選抜されたもので、すべてを網羅しているわけではありません。
その点が、5文型に分類する問題点としてずっと指摘されてきました。
文型は英文として認められるための条件ですので、英語学習者はしっかり理解する必要があります。
そこで高校などでは8文型を採用するところが登場しましたが、それでもすべてをカバーしていたわけではありません。
(ちなみに、アメリカの大学院で習ったときは48文型でした!)
いずれにしても、必要な文型は避けるわけにはいきませんので、以下、基本5文型を軸に、重要と思われる文型を紹介していきます。
2-1. S V:SがVする
この文型では、述語の内容を行う「ひと」や「もの」が主語の位置に置かれることが条件です。
以下のように、(1)「存在/生存/位置」、(2)「移動(行く・来る・向かう)」、(3)「機能」、そして(4)「走る」、「歩く」などの単純な行為ができる・できないが問題になる場合に登場します。
1) S exist/live/stand. (Sは存在/生存する/ある)
God exists. (神は存在する)
2) S come/go. (Sがやって来る/行く)
Spring has come. (春が来た)
3) S work/function (Sは機能する/効く)
The medicine works. (この薬は効く)
4) S walk/run/talk. (Sが歩く/走る/話す)
The dog talked? (その犬が喋ったって?)
注意点は、SVで終わらず、そのあとに修飾語が続くことが多いことです。
『ジーニアス英和辞典』では、その修飾語をMと表記していますので、確認してください。
MはModifier(修飾語)のMで、副詞か前置詞+名詞が原則として入ります。
例えば、live(住む) なら、S live (M)とあって、Mには「場所についての情報が入る」などと書かれています。
以下の例文をみてください。Mには下線が引いてあります。
1’) She lives in Australia. (彼女はオーストラリアに住んでいる)
2’) My daughter goes to elementary school. (娘は小学校に通っている)
3’) She works as a cook. (彼女は料理人として働いている)
4’) She runs fast. (彼女は速く走る)
1’) でliveが「住んでいる」という意味なら、「場所」などの情報がないと手持無沙汰です。
3’) で work が「働いている」なら、どんな仕事なのかまで示さなければ、「一区切りのまとまりある考え」にならないというわけです。
ここでの下線部Mは、伝達内容として重要なため、8文型に分類される場合はS V Mとして組み込まれていました。
Mは、Aと書かれたり、単に、「前置詞+名詞」などと記されたりします。
2-2. S V C:SはCである
この文型は、「SがCの状態にある」を示します。
以下の例文でも、5)では、「彼女」は「教員」という状態ですし、7)でも「その子供」は「怖れている」状態にあります。
この文型の特徴的な記号であるCはComplement(補語)から来ていますが、そうした関係を示す記号として登場します。Cが登場する文型はⅡのほかV(SVOC)だけです。
形態上のポイントは、Cの品詞です。
名詞(5)と形容詞(6)とに分かれ、形容詞の場合はそのあとに修飾語がつくこと(7)があります。
また、文型によっては、VとCの間に to be が入ります(8)。
5) S V C(名詞)
She is/becomes a teacher. (彼女は教員である/になる)
6) S V C(形容詞)
She is/feels happy. (彼女は幸せである)
7) S V C(形容詞) M
The child is afraid of dogs. (その子は犬が怖れている)
8) S V to be C(名詞・形容詞)
He appears to be a rich man. (彼は金持ちのようだ)
7)について。一般に文型を決める述語は動詞であることが多いですが、Vの位置にbe動詞が来て、形容詞が続く場合は、その形容詞が文型を決めます。
その場合形容詞によっては、M(副詞か前置詞+名詞)やthat節、不定詞が続きます。
以下のafraidがとる5つの文型をみてください。
7A) S is afraid of O
(SはOを怖れている )
7B) S is afraid for O
(SはOの安否が心配 )
7C) S is afraid to do
(Sは怖くてdoできない )
7D) S is afraid that 節
(Sは~が怖い )
7E) S is afraid
(Sは怖れている)
ここでの下線部も伝達内容として重要なので、S V C M(A)などとして、8文型に組み込まれていました。
2-3.SVO:SはOをVする
SVOは、SのほかにOがひとつ必要とされる文型です。
意味上は「好き・嫌い」や「創造」、「思考」と多岐に渡り、主な特徴はありません。
形態上は、Oに、名詞(9)、To不定詞(10)、動名詞(11)、that節(12)という3つの選択肢があるので、注意してください。
9) S V O(名詞)
Mary has dark hair. (メアリの髪は黒い)
10) S V to do
I forgot to do it. (私はそれをするのを忘れた)
11) S V doing
I like swimming. (私は泳ぐのが好き)
12) S V that節
I believe that he is kind. (彼は親切だと思う)
また、この文型にも、SVO以外に、意味上重要な情報が続くケースが多く、S V O Mなどとして8文型のひとつでした。
以下がそうした事例です。
13A) S remind O1 of(about) O2
SはO1にO2を思い出させる
13B) S fill O1 with O2
SはO1をO2で満たす
13C) S allow O to do
SはOがdoすることを許す
13D) S make O do
SはOにdoさせる
13E) S see O do/doing
SはOがdo/doing しているのを見る
13A)や13B)は、述語が2つの目的語を示す必要がある点で、2-4でみるSVOOに近いですが、5文型で考えると、SVOに入れざるを得ません。
13C)のようなOのあとにto不定詞が続く例もかなり多く、8文型には含まれませんでしたが、同等の扱いが必要です。
13D)は、使役動詞の例、13E)は知覚動詞(see, feel, hear, smellなど)がとる文型です。
2-4. SVO1 O2 :SはO1にO2をVする
この文型は、述語が主語のほかに目的語を2つ従えます。
学習用辞典では、O1 O2と数字が付され、O1は間接目的語、O2が直接目的語と呼ばれます。
ポイントは、O2に、名詞(14)、that節(15)、wh節(16)の選択肢があることです。
例文をみてください。
14) S V O1 O2 (名詞)
I asked John a question. (私はJohnに質問をした。)
15) S V O1 O2 (that節)
John showed me that he was honest. (Johnは私に彼が正直であることを示した。)
16) S V O1 O2 (wh節)
She told me why she had come. (彼女はなぜ彼女が来たのか話した。)
2-5.SVOC:SはOがCであるとVする/SはOをC(のまま)にする
この文型は、SがOがCという状態にいることを「判断する」(17)、「作る」(18)、「保つ」(19)という内容を伝えます。
以下、例文です。
17) S think/find/believe O (to be) C
I found this chair comfortable. (この椅子は心地よい)
18) S make/drive O C
Her words drove him mad. (彼女の言葉で、彼は怒った)
19) S hold/keep/leave O C
Jack held a door open for his wife. (Jackは妻のためにドアを開けておいた)
3.練習問題と回答
では、練習問題を考えてもらいましょう。
ひっかけ問題ばかりですので、辞書をよくみて、頑張ってください。
3-1. 練習問題
以下の英文の文型を指摘し、日本語訳をつけてください。
a) I feel bad.
b) I felt the cold pierced through my bones.
c) He would make a good husband.
d) He stopped to smoke.
e) The day turned out to be a fine one.
f) It turned out that I couldn’t do it.
g) His curiosity allows him no rest.
h) They allowed him to be a brave man.
3-2.回答
a) I feel bad.
S feel C.(SはCの気持ちである)で、「私は申し訳ないと思っている」という日本語訳になります。
S feel のあとはCかOかで悩みますが、Oは名詞しかなく、Cは名詞と形容詞の場合とがありますが、feel を辞典で確認すると、S feel CのCは形容詞しか来ません。
そこでこのような回答になります。
b) I felt the cold pierced through my bones.
S feel O do. (SはOがdoするのを感じる)という知覚動詞の文型(13E参照)です。
和訳は、「寒さが骨身にこたえた」となります。
c) He would make a good husband.
この文型もS make と来てOかCで悩みますが、S make C(名詞)で、「SがCになる」という文型です。
「彼はよい夫になるだろう」という訳をみてもわかる通り、結果として「SがCの状態になる」ことを示しています。
d) He stopped to smoke.
この文では、to smoke が問題になります。
stopping (動名詞)なら、S stop doing という文型と解釈され、「Sがdoing をやめる」という訳し方になりますが、動名詞ではありません。
したがって Ⅰの文型+修飾語(to 不定詞の副詞的用法:目的)となり、「彼は煙草を喫うために立ち止まった」という和訳になります。
文型で規定される、明示が義務付けられる情報以外は、すべて修飾語です。
d)は、文型と修飾語の区別ができるかどうか、という問題でした。
e) The day turned out to be a fine one.
S turn out to be C(SはCであることがわかる)という文型で、和訳は「その日は結局お天気になった」です。S V Cにto be が割り込んだ文型です(8参照)。
f) It turned out that I couldn’t do it.
ここでは、turned out の目的語が that節 にみえますが、主語の It の本当の内容が that 節で、S turned out(Sがわかった)というⅠの文型です。
和訳は、「私にはそれができないことが結局わかった」です。
g) His curiosity allows him no rest.
S allow O1 O2(SはO1にO2を与える)という文型で、「彼の好奇心が彼に休息を全く与えない」という和訳です。
h) They allowed him to be a brave man.
S allow O to be C(SはOがCだと考える)というVの文型で、「彼らは、彼が勇敢な男だと考えた」になります。
4.文型を見分けるコツ
いかがでしたか。
繰り返しになりますが、英文の文型がどういうものかをわかることは英語の勉強のスタートです。
全て正解だった方は、次は、修飾語が入った英文にチャレンジしてもらうことになります。
残念ながら、正答率があまり良くなかった方は、これから紹介する文型を読み解くコツをお読みになり、試していただきたいと思います。
コツは、ズバリ、基本5文型にしばられないことです。
目の前の英文がどんな文型を骨格に持っているのかを探すとき、基本5文型に照合すると、ピントがずれてしまいます。
なぜなら、英語の全文型から抜き出した、たった5つでしかないからです。
例えば、CとOの区別が難しい場合、唯一の違いは品詞で、Cが名詞か形容詞、Oが名詞ですね。
では、Cに名詞が入っていたらどうやって区別するのでしょう。
そこでまず文型の本質、述語の内容に応じて英文として認められる条件を辞典で調べて、本当の選択肢を確認します。
練習問題のa) とb) を解くのなら、以下が選択肢です。
S feel C(形容詞) S はCの気持ちである
S feel like O(名詞) SはOのように感じる、Oを飲みたい・食べたい気がする
S feel like doing Sはdoing したい気がする
S feel O(名詞) SはOを気づく、感じる、触って調べる
S feel O to be C(形容詞) SはOがCであると感じる
S feel O do/doing SはOがdo/doingするのを感じる
Cの品詞は形容詞で統一されていますから悩むことはありませんし、基本5文型よりはるかに明瞭に選択肢が浮かび上がります。
おススメの勉強方法としては、主要な述語がとる文型を上記のようにまとめたノートを作ることです。
アメリカの大学院に留学している時はいつも持ち歩いていました。
終わりに
今回のテーマは、「英語の語順」でした。
基本5文型は、英文として認められる条件のなかで基本的なものですが、実際に文型を見分けるとなると、もう少し視野を広げると同時に、文型の本質を見据える必要があります。
みなさんの英語学習の一助となりましたら幸いです。

茨城県出身。筑波大学在学時に、JICAにてインターンを経験し国際問題に興味を持つ。日本に拠点を置きながら英会話をマスター。その他、タイ語、ベトナム語等も国際交流の中で学ぶ。 ボランティア活動の為海外へ何度も足を運びました。 そこで触れ会った文化や生活などリアルな声を知ってほしいとブログを開始。 趣味はオーガニック製品を集めること。ダイビング、登山など自然に触れることが大好きです。