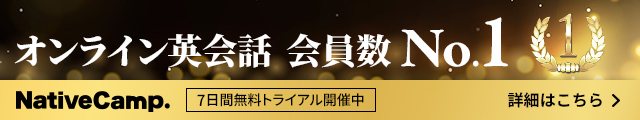一段と寒さが深まり、冬の足音が聞こえてきました。これから12月下旬の「冬至」に向けて、日に日に夜が長くなっていきます。
今回のコラムでご紹介するのは、「冬至」の英語表現。今年2023年は12月22日が冬至です。
日本では、この日にゆず湯に入ったりかぼちゃを食べたりする習慣がありますが、海外ではどのように過ごすのでしょうか。冬至にまつわるエピソードを交えてご紹介します。一緒に「夏至」や「春分」の表現も覚えていきましょう。
「冬至」の英語表現
今回は、以下の英語表現をご紹介します。
・summer solstice(夏至)
・vernal equinox(春分)
・autumnal equinox(秋分)
・The beginning of spring(立春)
・the beginning summer(立夏)
・the beginning of autumn(立秋)
・the beginning of winter(立冬)
Solsticeやequinoxは耳慣れない単語かもしれませんが、語源を理解すると覚えやすくなりますよ。早速見ていきましょう。
winter solstice
「冬至」は英語で「winter solstice」と表現します。
solsticeの語源は、sol(太陽)とsistere(静止する)からなるラテン語のsolstitiumです。これは「太陽が静止しているように見える点」に由来し、天文用語で「至点」といいます。
至点は年に2回あります。正午の太陽の位置が一年でもっとも低い日を「冬至」、反対にもっとも高い日を「夏至」と呼びます。北半球では12月が冬至、6月が夏至となりますが、南半球では逆転し、12月が夏至、6月が冬至になります。
冬至は、暦を知るための重要な指標として、古来より利用されていました。農作物の種まきや冬季に備えて食糧を備蓄する時期を、天体の位置によって把握していたのです。
太陽の語源である「sol」は、「solar(ソーラー、太陽の)」「parasol(日傘)」などでも用いられていますよ。イタリアの良く知られたカンツォーネ『オー・ソレ・ミオ('O sole mio)』にも、「sole(イタリア語で“太陽”)」という単語が登場しますね。
今日は冬至です。
今年の冬至は、12月22日です。
日本では冬至の日にゆず湯に入るよ。アメリカでは何か特別なことをするの?
冬至の過ごし方
冬至という現象は、地球の地軸が太陽の周りを公転する際に描かれる平面(公転面)に対して、垂直より約23.4度傾いているために起こります。この傾きによって、太陽の当たる時間が変化します。
フィンランドの北部や北極では、冬至の前後になると一日中太陽が沈んだままの「極夜(英語でPolar night)」という期間が発生します。スウェーデンやデンマーク、ノルウェーなどの地域も同様に、冬の間は日照時間が極めて短く、わずか数分しか太陽が昇らないこともあるそう。
冬が長い地域に暮らす人々にとって、太陽のありがたみは推して知るべしでしょう。冬至の日を境に太陽が再び力を取り戻していくことから、この日は古来より重要な意味を持っていました。
キリスト教伝来以前から、ケルトやゲルマン民族の間では「ユール」という冬至の祭りが祝われていました。後にユールはクリスマスの風習と融合していきます。
例えばクリスマス・ツリーはゲルマン民族の巨木信仰に由来しているといわれています。また、クリスマスの定番ケーキ、ブッシュ・ド・ノエルは、太陽の復活を祝って燃やす薪「ユール・ログ」を模したものです。
地軸がわずかに傾いていたことから冬至のお祭りが生まれたことを考えると、とても不思議ですね。
キリスト教圏では、クリスマスと冬至は密接な関わりがある。
冬至を過ぎると、徐々に日照時間が伸びていく。
冬至の関連表現
「至点」を表すsolsticeを理解したところで、関連表現も見ていきましょう。
夏至
冬至とは反対に、一年でもっとも日が長い「夏至」。英語では「summer solstice」と表現します。
冬が長く夏が短い分、北欧では夏至を盛大にお祝いします。スウェーデンでやフィンランドでは、夏至に合わせて毎年6月下旬頃が移動祝祭日となります。
家族で湖畔や森の中にあるサマーコテージに出かけて、美しく短い夏を満喫するのが北欧流の楽しみ方だそう。
より身近な表現として「midsummer」があります。夏至祭では、ミッドサマーポールと呼ばれる柱を立てて、その周りを踊ったり歌ったりする風習があります。
ちなみにシェイクスピアの戯曲『夏の夜の夢』の原題は、「A Midsummer Night’s Dream」。夏の夜というと、日本のうだるような熱帯夜を想像してしまいますが、実は夏至の頃の物語だったんですね。
夏至が近づき、日がだいぶ伸びてきた。
北欧は冬が長いため、北欧の人々は短い夏を満喫する。その一つが夏至を祝う「夏至祭」だ。
B: I'm planning to go to the summer cottage with my family again this year.
A: 今年のミッドサマーはどんなふうに過ごすの?
B: 今年も家族でサマーコテージに行く予定だよ。
春分
春分は英語で「spring equinox」、または「vernal equinox」と表現します。
「Equinox」は、天文用語で「分点」という意味。分点とは天球上で黄道と天の赤道が交わる点のこと。太陽が南から北へ通過する点を春分点、北から南へ通過する点を秋分点といいます。
equinoxはあまり目にする機会のない単語ですが、語源は明快です。Equi-(均等な)とnox(夜)が結合してできた単語で、そのまま理解すれば「昼と夜の長さが等しくなる日」という意味になります。
「春の、春に起きる」などの意味をもつ形容詞「vernal」+equinoxで「春分」、「秋の」を意味するautumnal+equinoxで秋分となります。
2024年の春分の日は3月20日。ちなみにキリスト教圏ではこの時期にイースターが祝われます。イースターの日付は、「それぞれの年の春分の日の直後に来る満月の次の日曜日」と決められています。とてもややこしいですね。したがって、2024年のイースターは、西方教会では3月31日、東方教会では5月5日となります。
日本では春分の日は国民の祝日にあたります。
春分や夏至などの天文現象は、農作業の目安として利用されてきた。
立春・立夏・立秋・立冬
最後に、立春、立夏、立秋、立冬の英語表現をご紹介します。
これらは、二十四節気に由来する言葉です。二十四節気とは、春分点を起点に一年を二十四の季節に分けた暦。2500年以上前に中国で作られ、平安時代に日本に伝来したと考えられています。
二十四節気は英語圏では用いられていないため、直訳できる単語はありません。よって、立春や立冬を英語で表現したいときは、「the beginning of spring(春の始まり)」などと言い換えると良いでしょう。
それぞれ下記のように表現できます。
the beginning of summer(立夏)
the beginning of autumn(立秋)
the beginning of winter(立冬)
立秋は日本の暦の上では8月上旬だ。
日本には、二十四節気をさらに72個に分けた「七十二候」が存在しますね。日本ならではの細やかな季節の変化を、英語では「micro-seasons」と表現します。
日本の暦には、72の細やかな季節があります。
まとめ
「冬至」の英語表現と、関連表現をご紹介しました。「冬至」「夏至」は至点を意味する「solstice」、春分と秋分は分点を意味する「equinox」という単語を覚えておきましょう。
海外と日本では暦も大きく異なるため、直訳できる単語ばかりではありません。単語の意味を紐解いていくと、それぞれの風土を色濃く映し出されていることがわかりますね。英語を勉強する際に、ぜひ地域の風習についても学んでみてください。

◇経歴(英語を使用した経歴)
アメリカの四年制大学に留学
◇英語に関する資格(資格、点数など)
大学入学時にTOEFL580点を取得
◇海外渡航経験、渡航先での経験内容(仕事、留学、旅行など)
高校卒業後に留学し、アメリカ、ニューヨークの四年制大学を卒業
アメリカ国内の他に、カナダ、ドイツ、ポーランド、香港を旅行得
◇自己紹介
ライター/編集者/時々漫画家
出版社、広告代理店を経て、現在は編集プロダクションに勤務しながらフリーランスのライターとしても活動。さまざまなマイノリティが住むブルックリンに滞在していた経験から、人種・ジェンダー・貧困などの社会問題に関心を持つようになり、現在の活動の軸となっている。好きなものは大型犬。

I took a Bachelor of Science degree in Mathematics where my problem-solving and critical-thinking skills were honed. I have worked as a trainer in a government office, which has helped me to develop my communication and intrapersonal skills. My hobbies are reading, listening to music, and cooking. After joining NativeCamp, I acquired 2 years of teaching experience. Currently, I am involved in content production in the Editing Department.