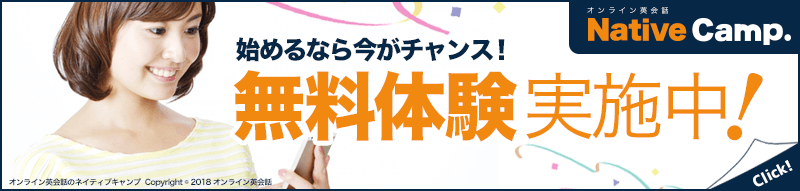「英単語が覚えられない!どうやって暗記したらいいの?」
「そもそも英語の勉強は英文を丸暗記するしかないの?」
「英単語を勉強する意味は?」
この記事ではこういった疑問に答えていきます。
英語学習をする中で、必ず出てくるのが、
「英単語」を覚えるということですよね。
しかし意味もなく、何千もの単語をひたすら暗記していくのは非常に苦痛に感じますし、そもそもなぜ英語学習を暗記しなくてはならないのか、このように疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
高校や大学受験など一般入試対策を頑張っている受験生、英検や定期テストのために単語力をつけようと頑張っている方、避けて通れないのが英単語の暗記です。
どんな言語もそうですが、必ず最初は単語を覚えるところから始まりますよね。
日本人は、義務教育の過程で、あまりにも
「覚えること」を強要されすぎて、英単語を学習する意味を忘れてしまいがちです。
「でも、TOEICや受験勉強のためには覚えなくてはいけないし・・・・」
と覚えなくていけない理由があるのも事実です。
そこで今回は、そういった英単語の暗記について悩んでいる方に向けて、絶対に忘れない英語勉強法についてご紹介していきます。
- 英語学習は暗記するしかないの?
- なぜ英単語を覚える必要があるのか?
- 英単語学習のやり方は?忘れにくい学習法
- 記憶の忘却曲線と記憶力の関係性
- 英単語を効率よく暗記するための3つのコツ!
- あなたの目的別、英単語暗記についてアドバイス
- まとめ
英語学習は暗記するしかないの?
そもそも、英語学習は暗記するしかないのでしょうか。
多くの英会話学習者の方は、英語学習は暗記をするしかないと思っていることが多いです。
勉強量をひたすら増やして、量が質に転化するまで頑張っている、また、英語とはそういうものだから、と割り切って英語学習をしている方がほとんどです。
しかし、
「英語=暗記科目」
だと思い込んで、片っ端から英語を暗記しようとするのは、英語学習のやり方として相応しくない場合もあるのも事実です。
英語とは、本来言語なので、
「この単語は意味が3つある」
「この使い方はこういう意味で、こういった使い方もある」
などのように、日本語の堅苦しい文章で説明されているようなものではありません。
にもかかわらず、こういった単語帳や文法などの説明、表記を鵜呑みにして、全部丸暗記しようとする方が非常に多いのです。
確かに、英単語を暗記することで語彙力が向上したり、リスニングの時にキーの単語がわかっただけで、聞き取れたりと色々とメリットがあることも多いです。
ただ、極力効率的に、そして使える英単語を覚えるためには、単純に全ての単語を丸暗記するのではなく、効率よく、実践的に英単語を覚えることが必要なのです。
つまり、英語学習はただ暗記するだけではなく、暗記した上で意味を理解しなくては意味がないのです。
なぜ英単語を覚える必要があるのか?
では、さらに英単語を覚える意味を深掘りしてみましょう。
実は英語というものは、基本的に「単語」「文法」「発音」の3つの要素で成り立っています。
英語学習が果たしてこんなにシンプルなのか具体的にそれぞれの要素について解説していきます。
まずは、「単語」です。
英語というものは必ず英文という形で存在しますよね。
これは口語であっても、文体であっても必ず英語の文章として存在しています。
“This is a pen”
これはペンです。
以上のようなごく簡単な英語でも、「This」「is」「a」「pen」という4つの単語から成り立っています。
そして、この4つの単語は「文法」という規則によって並べられているため、意味を成しているのです。
もし“Pen a is this”という風に並んでいたら意味を成さないですよね。
これが文法が必要な理由です。
さらにこの文法を出力するために「発音」という方法を使って、「英会話」は成り立っているのです。
この例文の意味が分からない方はいないとは思いますが、もしこの単語の意味が全く分からなかったらどうでしょう。
英語が正しい文法で並んでいても、相手の口から発音されても、全く理解することはできませんよね。
このように英単語学習は、その言葉の「意味」を理解するために、非常に重要で、なくてはならない学習過程なのです。
英単語学習のやり方は?忘れにくい学習法
英単語を学習することがいかに大切か理解してもらったところで、次に忘れにくい英単語の学習方法について解説していきます。
普段から英語を学習している方で、英単語を覚える時に、「この単語覚えていたのに、ついつい忘れてしまう」なんてことありませんか?
単語帳を1周したのに、忘れてしまっている単語があったり、そもそも覚えたこと自体忘れてしまっている単語があることに気づくはずです。
実は、これは記憶の忘却曲線と記憶力が関係しているのです。
記憶の忘却曲線と記憶力の関係性
みなさんは、「エビングハウスの忘却曲線」の話を聞いたことはあるでしょうか。
これはドイツの心理学者であるヘルマン・エビングハウスによって証明された、ある学説のことです。
この研究で彼は人間の脳と記憶力の関係について興味深い結果を出しました。
それは、「人間の脳は、そもそも復習しないと忘れるように出来ている」ということです。
彼は、記憶に関する実験として「子音・母音・子音」から成り立つ無意味な音節(rit, pek, tas, …etc)を記憶し、その再生率をグラフにして曲線を書きました。
その結果、具体的に以下のような忘却に関する結果がでたのです。
20分後には42%忘れる
1時間後には56%忘れる
9時間後には64%忘れる
1日後には67%忘れる
2日後には72%忘れる
6日後には75%忘れる
31日後には79%忘れる
この研究では、なんと一日経つだけで、記憶のおよそ7割近くは忘れてしまうということが分かりました。
忘却曲線の研究は意味を持たない単語について記憶しているので、英単語については、もう少し緩やかな曲線になるかもしれませんが、大半の記憶が短期間に失われてしまうという事実は、同様です。
「この曲線通りに行くと、勉強しても忘れてしまうから意味がないのでは?」と思ってしまう方もいるかもしれません。
しかし、この忘却曲線は「復習」という作業を行うことで、防ぐことが出来るんです。
言ってみれば、復習によって短期記憶を長期記憶に変換できるということです。
長期記憶のひとつに「エピソード記憶」というものがあります。
自分の経験にもとづいたエピソードなどの情報を覚えたい単語や表現と合わせて覚えていく方法です。
感情にもとづく記憶ほど、長く定着します。
例えば、72%忘れている2日後の時点で、一度復習をするとしましょう。
ここで記憶は100%になります。
すると、次に1週間後にデータを取ると、忘れている部分は50%くらいになります。
これまでは、1日で70%以上も忘れていたのに、次の日に復習するだけで、7日間も忘却速度が保たれるのです。
もちろんこの調子で、学習し続ければ、最終的には100%の暗記につながるのです。
反復するタイミングを意識して復習する
人間の記憶は適切なタイミングで復習すると、定着率が圧倒的に良くなることは分かりました。
英単語も同様に、この忘却曲線の結果を意識して復習をすることによって、必ず今までの学習定着度との差を図れるはずです。
ここでは、英単語200語を覚える時の1週間の学習計画を例にとって考えてみます。
まず、単語を40語ずつに5等分します。
それから、先ほどの忘却曲線を意識して復習すると、以下のような計画になります。
1日目
① (1回目)
2日目
① (2回目)
② (1回目)
3日目
②(2回目)
③(1回目)
4日目
③(2回目)
④(1回目)
5日目
④(2回目)
⑤(1回目)
6日目
⑤(2回目)
①(3回目)
7日目
②(3回目)
本当はこの7日目からは、新しく40~50語を追加で覚えるようにすると、どんどん継続的に覚えていくことが出来ます。
今回は、次の日の後、6日目に3回目の復習を入れていますが、7日目でもいいですし、自分が覚えたい量がもっと多いのであれば、1度に覚える単語量を増やしてみてもいいかもしれません。
とにかく忘却曲線を意識して、復習を繰り返していけるように心がけましょう。
英単語を効率よく暗記するための3つのコツ!
ここまでは、勉強の計画や記憶の方法など、概要的なことについてご紹介してきました。
どのように記憶していくと、単語を覚えやすくなるのか、自分の計画を作ってみるといいかもしれません。
ここからは、もう少しテクニック論に寄って、多くの学習者の方が知りたいであろう、「覚え方」について詳しく解説していきます。
1.単語の意味を十分に理解する
最初は単語の意味を十分に理解することが必要です。
暗記すると言っても、ただ単語を「単語」として覚えても意味がありません。
しっかりと意味を確認することが重要なのです。
さらに意識して欲しいのが、「意味のその先にあるニュアンス」について意識して覚えるということです。
仮に、“adopt(採用する)”という単語を覚えようとした時に、「採用する」とそのままの日本語で理解するのではなくて、「何かの計画や決議などを採用する」というイメージを持って覚えるのが重要です。
このような方法を「フラッシュバック法」と呼びます。イメージという映像を脳に焼き付ける暗記方法です。
なぜこれが大事なのかというと、基本的に英語が話せるようになるためには、「英語脳」にならなくてはいけません。
「日本語脳」というのは、日本語を頭で考えて、その内容を一度翻訳して、英語にしてから話すという考え方です。
単語を日本語として覚えるのではなくて、英語を英語として覚えるためにも、イメージを持って覚えられるようにしましょう。
2.自分が使う場面をイメージして発音する
音声として定着させることも大切です。
次に、先ほどの「イメージ」を軸にして、実際に発音してみましょう。
実際に発音して覚えることで、正しい発音で英語を言えるようになりますし、単語の概念を理解した上で覚えることが出来るようになります。
自分が使う場面をイメージして、しっかり発音出来るように工夫しましょう。
3.単語を使った文を作って使ってみる
最後に、その覚えた単語を使って、簡単でもいいので文を作ってみましょう。
この部分は、ステップの中でも時間がかかる部分で、いくら時間があっても足らなくなってしまいます。
文を作る際は、本当に簡単な1文でいいので作って発音してみると、より具体的にイメージを捉えて、定着するようになります。
大変ではありますが積極的に覚えた単語で文を作って、使ってみるようにしましょう。
最後に、英語学習の目的別に英単語暗記についてのアドバイスをお届けします。
あなたの目的別、英単語暗記についてアドバイス
英語学習をする目的は人それぞれです。
従って、英単語の暗記についても、単語テストや塾に通う学生と、TOEIC単語、ビジネス英語や海外旅行を目標にする社会人では、その内容が違ってきます。
また、学習にかけられる時間、年齢によって多少暗記力も違うでしょう。
学生のためのアドバイス
これまで解説してきた英単語の勉強法を参考に、なんども覚えた単語の復習をしてください。
復習とともに、必要なことにアウトプットがあります。家族や友人へ、または近くにある教会などでアウトプットの機会を作り、覚えたことをどんどん使いましょう。
経験がともなう暗記は英単語をみて頭のなかで繰り返すのと比べて、定着が違います。
社会人のためのアドバイス
仕事を持つ社会人が限られた時間で英単語の暗記をするにはルーティン化が必須です。
それには、気軽にできるアプリの活用も効果的でしょう。
選ぶ英単語の種類も、自分の業種にあったもので実際に仕事に関するものや、海外で体験してみたい趣味の世界など、自分にかかわるものにしてそれらへの興味とともに学習を進めます。
また、TOEIC受験をいつにするか決め、それに向かって英単語の暗記を頑張るように自分に期限をかすのも有効です。
自分が現状どれくらいできるのか調べてから、学ぶ単語のレベルを決めることもできます。
「Test Your Vocabulary」は簡単に調べることができますので、まずチェックしてみてくださいね。
Test Your Vocabulary:
http://testyourvocab.com
まとめ
今回は、英語学習者の方に向けて、英単語を覚える意味や、どのようにすると英語が勉強できるようになるのかについてご紹介してきました。
英単語の学習は、確かに長くて辛いものかもしれませんが、ずっとそのようにして暗記を続けていても続きませんし、出来るようになりません。
また、そうやって覚えた単語は、実際に使えない意味のない単語であることが多いです。
暗記をするポイントは、「反復する」「使って覚える」ということです。
インプットとアウトプットを上手く組み合わせて、どんどん定着させましょう。
英単語の暗記に苦しんでいる方は、是非とも本記事を参考にして、単語学習に取り組んでみてくださいね。

【現在の仕事】
Webライター
【経歴・職歴】
・法政大学文学部出身
・学生時代はBBQ場でのアルバイト、プログラミングスクールを運営する企業、レシピ動画メディアを運営する企業にてインターンを経験。
バックパッカーとして海外旅行もしていました。
・部活動:小学校~高校まで野球をやっていました。
【趣味】
「スケートボード/スノーボード」「野球」「旅行」「料理」など

I took a Bachelor of Science degree in Mathematics where my problem-solving and critical-thinking skills were honed. I have worked as a trainer in a government office, which has helped me to develop my communication and intrapersonal skills. My hobbies are reading, listening to music, and cooking. After joining NativeCamp, I acquired 2 years of teaching experience. Currently, I am involved in content production in the Editing Department.