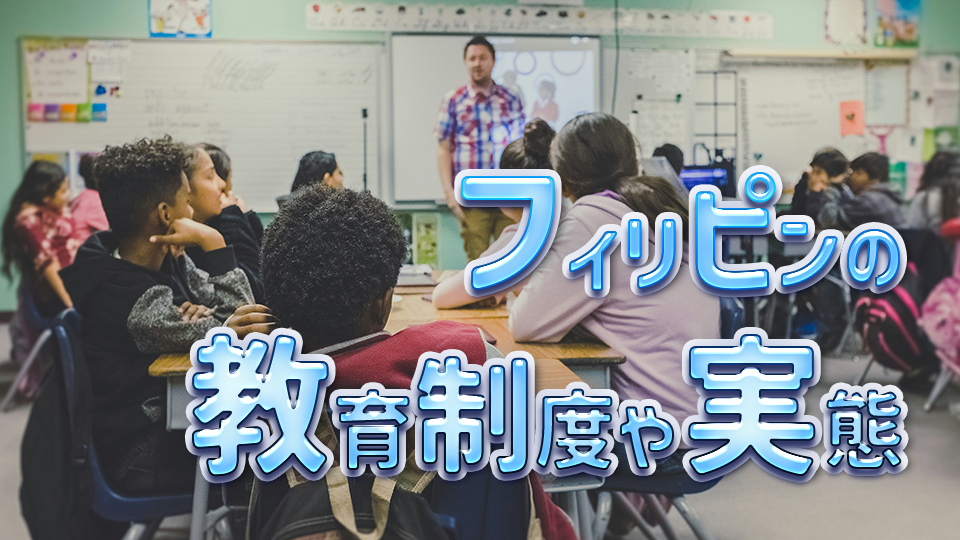
近年ではASEAN主要国の中でもトップクラスの経済成長率を誇っているフィリピンですが、教育制度やその実態はどのようになっているのでしょうか。
フィリピンは留学や旅行先としても人気が高いため、教育面についても関心を持つ方は多いでしょう。
この記事ではフィリピンの義務教育や教育制度の実態を徹底解説し、問題点を掘り起こします。
フィリピン教育制度の特徴
まずは、フィリピンの教育制度の特徴を見ていきましょう。
フィリピンの教育制度には以下の5つの特徴があります。
・夏休みは7月と8月の2カ月間
・小学校でも希望の学校へ進めない場合がある
・小学3年生からは英語で授業を受ける
・高校は成績で昼と夜に分けられる
公立と私立の学校で格差が大きい
フィリピンの学校には公立と私立があります。
そのため、学校数は私立の方が多いのですが、生徒の総数は公立学校の方が圧倒的に多いです。
公立学校では1クラス40〜50人もの生徒が授業を受け、教室にはエアコンがなく勉強に集中するのも難しいような状況です。
また、日本のように教科書が学校から無料配布されません。
学校が生徒に教科書を「貸し出す」システムとなっているため、ボロボロに傷んだ教科書を使うこともあります。
しかも教科書の内容は数年に一回しか見直されないため、情報が古くなっていることもしばしばです。
その一方、私立の学校だと毎年内容が更新されるため、公立との間に学力格差が生まれる一因となっています。
夏休みは7月と8月の2カ月間
フィリピンの学校の長期休暇は幼稚園から大学まで同じで、7月と8月の2カ月間です。
夏休みの間、裕福層の子供たちの多くは海外旅行や国内旅行に出かけますが、一般家庭では日常と同じ過ごし方をしています。
中学生以上になると夏休みにアルバイトや家の仕事の手伝いをして学費や生活費を稼ぐなど、貴重な稼ぎ時として過ごす子供も多くいます。
小学校でも希望の学校へ進めない場合がある
日本では公立の小学校は区域ごとに割り当てられているので、入学できないということは通常あり得ません。しかし、フィリピンでは違います。
入学するには、親が先生と面接したり家庭訪問を受けたりする必要があるのです。
もし入学希望者が予定数を上回っていた場合は、入学を断られることもあります。
このようにフィリピンでは、たとえ公立小学校であっても学校から認められないと入学することができません。
小学3年生からは英語で授業を受ける
フィリピンでは、小学3年生からは英語で授業を受けます。
裕福層の子供は小学校入学前から英語の教室に通っていて、親も高等教育を受けているため英語を話せます。
しかし貧困層の子供は親も英語がよくわからないため授業についていけず、裕福層との間に大きな格差が生まれているのです。
高校は成績で昼と夜に分けられる
フィリピンでは小学6年生の7月に行われる試験で上位の成績の子供は昼間の高校、下位の子供は夜間高校へと振り分けられます。
なぜこのようなシステムになっているかというと、子供の数が多くて教室が不足しているからです。
フィリピンでは20歳未満の人口が約44%を占めているため、教育設備や教師の数が圧倒的に不足しており、とくに農村部において大きな問題となっています。
フィリピンの義務教育期間は何年?
フィリピンの義務教育は、幼稚園1年、小学校6年、高校6年の合計13年間です。
この「1-6-6制」は「K-12制度」と呼ばれ、日本の義務教育である9年間よりも4年も長いことになります。
幼稚園の1年間は基礎教育、小学校では基礎学力の養成を行い、高校6年間の最初の4年間(ジュニアハイスクール)で基礎学力を深めます。
さらに残りの2年間(シニアハイスクール)では専門スキルを学び、社会に出たり大学で学ぶための準備教育のための期間となります。
フィリピンの教育格差とは
フィリピンでは、裕福層と貧困層の教育格差が大きな社会問題となっています。
ここでは、フィリピンの教育格差について解説していきましょう。
・学費以外にも教育費がかかる
・裕福層と貧困層で通う学校が違う
裕福層と貧困層の学費格差が大きい
下は、フィリピンの世帯年収と年間の学費支出を表にまとめたものです。
| 世帯年収 | 1年間の学費 | 収入に占める学費の割合 |
| 10万~25万ペソ未満 | 2,158ペソ | 1.5% |
| 25万~50万ペソ未満 | 6,354ペソ | 2.3% |
| 50万ペソ以上 | 23,123ペソ | 4.1% |
しかし、世帯年収25万~50万ペソのやや裕福な家庭の1年間の学費は6,354ペソと、一般家庭の約3倍です。
さらに、世帯年収が50万ペソ以上の富裕層になると、学費は23,123ペソで、一般家庭の10倍に跳ね上がります。
このように、フィリピンでは一般家庭と裕福な家庭の学費格差が非常に大きくなっています。
学費以外にも教育費がかかる
教育費として必要なのは、学費だけではありません。前述したのは学費と入学費です。
学校に通うためには、学費と入学費以外に制服や教科書、文具、参考書などを購入する必要があります。
また、公立の学校にはスクールバスや給食がないため、通学費と昼食代もかかってきます。
以下は、フィリピンで公立の小学校へ1年間通うために必要な費用の概算です。
・制服・くつ・カバンなど:2,000~2,500ペソ
・文房具・その他雑費:4,800ペソ
合計すると、約9,000ペソになります。
しかもフィリピンの多くの家庭では3人程度の子供がいるため、9,000ペソ×3=27,000ペソが必要です。
フィリピンの平均年収は17万ペソなので、収入の15%を占めることになります。
貧困層だと収入はさらに少なく、年間収入が10万ペソ未満である家庭も多いことを考えると、教育格差がいかに大きな問題であるかがわかるでしょう。
裕福層と貧困層で通う学校が違う
前述したように、フィリピンには私立と公立の学校があります。
しかし、私立の学校に通うには大きな費用がかかるため、一般家庭のほとんどの子供たちは無料の公立学校へ通うことになります。
では、公立学校なら格差のない教育が受けられるかというと、そうではありません。
フィリピンでは公立学校においても収入によって大きな格差があります。
たとえば特別授業や、教科書を補う補助教材は有料です。
学校が遠いと交通機関を利用する必要がありますが、貧困家庭の子供は歩いて通学するしかありません。
また、家庭で勉強するにはインターネット環境やプリンター、パソコンなどが必要になります。
フィリピンでは裕福層と貧困層の通う学校が違うため受けられる教育に大きな格差がある上に、公立学校に入学した場合にも格差があるといえます。
学校に行けない子供の現状
ここまで、フィリピンの教育制度や、貧富の差による教育格差についてお話ししてきました。
フィリピンの貧困家庭では、子供たちがストリートチルドレンとして働いたり、孤児院に預けられるケースが数多くあります。
ここでは、以下について解説していきましょう。
・孤児院に預けられる子供
ストリートチルドレンとして働く子供
フィリピンでは路上で生活しながら働く
「ストリートチルドレン」と呼ばれる子供たちが大勢います。
親は優秀な子供ひとりに教育を受けさせるのが精一杯で、他の子ども達は実質的に育児放棄状態となります。
そんな子供たちの多くがストリートチルドレンとなって、働きながら路上で生活するのです。
ストリートチルドレン達が悪い大人に利用されて、スリなどの犯罪を犯すケースが多発しています。
本当の加害者は指示する大人達であり、ストリートチルドレンは貧しい社会の犠牲者だといえます。
孤児院に預けられる子供
フィリピンの貧困家庭では、生まれてきた子供を育てる経済力がなく孤児院へ預けるケースが多くあります。
しかし、家族と一緒に路上生活を送っている子供の中には、素行に関する問題や家庭環境の理由から孤児院にも入れない場合があります。
彼らは学校に行くこともできず、路上やスラムで生活しているのです。
フィリピン教育問題の実態
フィリピンでは2021年の改革によって、基礎教育が幼稚園1年と小学校6年、中等教育が高校の6年と、計13年間に定められました。
下は、学校種別と男女別の終了率を表した表です。
| 学校種別 | 終了率(全体) | 男子の終了率 | 女子の終了率 |
| 小学校 | 91.9% | 89.0% | 95.2% |
| 中学校 | 81.0% | 74.9% | 87.7% |
| 高校 | 78.3% | 73.9% | 83.4% |
小学校から高校へと教育段階が上がるにつれて終了率が低下しています。
特に男子の方が女子に比べて終了率が低く、教育段階ごとの低下も顕著となっています。
終了率が低下する原因はやはり貧困にあります。
年齢が高くなるにつれて家族の一員として労働に付くことが求められるからです。
男子においては女子以上に働き手としての期待が大きいため、さらに終了率が低くなっています。
フィリピンの教育水準について
フィリピンの教育水準は、2019年に行われた国際学力調査の読解力で79カ国中最下位、数学と科学はいずれも最下位から2番目と非常に低い結果となっています。
大きな経済成長を遂げているフィリピンですが国民の資産には反映されておらず、貧富の格差は依然としてなくなっていません。
GDPは2倍になったにも関わらず、世帯収入や支出額は1.2~1.3倍にしか成長していないのです。
経済格差や貧困の問題がフィリピンの教育水準にも大きな影響を与えているといえるでしょう。
まとめ
この記事では、フィリピンの教育制度やその実態について徹底解説しました。
フィリピンでは経済成長の結果がまだ国民生活には反映されておらず、多くの子供たちがストリートチルドレンとして生きざるを得ない状況です。
経済格差による教育の格差は大きく、多くの子供たちが通う公立学校の環境も決して十分ではありません。
フィリピンの子供たちの現状を救うには、日本をはじめ世界各国が協力して支援する必要があるといえます。

◇経歴
VRChat(メタバース空間でのチャット)というゲーム上でいろんな国の方とお話ししてます。
◇資格
英語検定2級
◇留学経験
ありません
◇海外渡航経験
イタリア、フランス、スペイン(いずれも旅行)
◇自己紹介
VRChatというゲームを通して大勢の海外の方と知り合ったのがきっかけで、2年前に独学で英語学習を始めました。
高校卒業後全く英語に触れていなかったので、基礎英語から始めて2024年の夏に英検2級を取りました。
2025年は準1級を目指します!
まだまだ英語初心者ですが、皆さんと一緒に頑張っていけたら素敵だと思っています。




